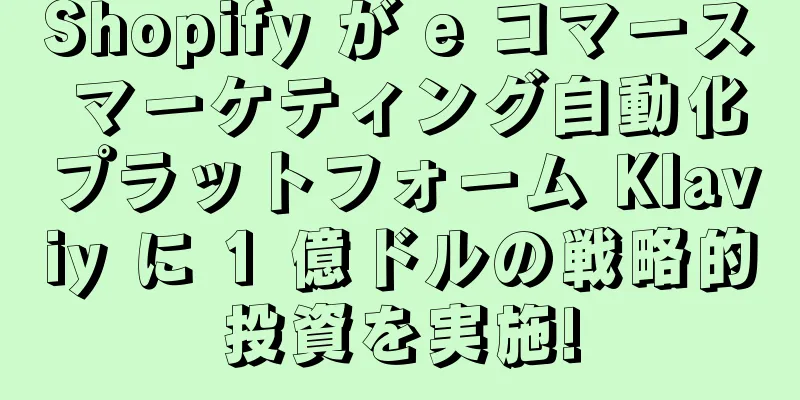親知らずはなぜ生えるのでしょうか?

|
親知らずが生える時、多くの人にとってとても痛いので、親知らずが生える理由を理解するように注意する必要があります。実際、親知らずが生える人は多く、親知らずが生える時、歯茎が腫れて痛んだり、歯周炎や歯髄炎を起こしたりしやすくなります。 1. 親知らずは、学術的には第3大臼歯と呼ばれ、一般的には智歯、根生歯、末期歯とも呼ばれ、口の中で喉に最も近い歯です。すべて生えると、上顎と下顎に2本ずつ、合計4本の歯になります。親知らずは通常、16歳以降に生えてきます。乳児期に生えてくる乳歯や、小児期に生え変わる永久歯に比べ、親知らずは、人間の精神が成熟したときに生えてくることが多いため、この名前が付けられています。親知らずの生える時期は個人差が大きく、20歳未満で親知らずが生える人もいれば、40歳や50歳で親知らずが生える人もいれば、一生親知らずが生えてこない人もいます。これはすべて正常なことです。さらに、4 本の親知らずがすべて完全に生えてくるとは限りません。親知らずが 1 本か 2 本しか生えてこない人もいれば、途中で成長が止まってしまう親知らずもあります。このような状態を埋伏智歯といいます。親知らずはどこにありますか? 前歯の隙間から、片側の前歯から何本歯あるか数えます。8本目の歯があれば、それは親知らずです。 2. 親知らずが原因となる病気はありますか? 親知らずは特殊な位置にあるため、その清掃や治療には多くの問題が伴います。一般的な病気としては、虫歯(一般に虫歯として知られています)、歯周炎、歯髄炎などがあります。 親知らずは歯の一番奥にあるため、毎日の歯磨きではきれいにしにくく、虫歯になりやすいです。親知らずは、生えるスペースが足りないために腫れや痛みを引き起こすことが多く、また、隣の歯を侵食して歯痛を引き起こすこともあります。さらに、親知らずは、対合歯が不足しているために過剰に生えてきて噛み合わせに影響したり、十分に生えてこず埋伏歯となり不正咬合、歯冠周囲感染症、口を開けにくくなるなどの症状を引き起こすことがあります。 親知らずは3番目に大きい大臼歯であり、隣接する第二大臼歯に大きな影響を与えます。ほとんどの親知らずは埋没歯で前方に傾いているため、第2大臼歯を約45度の角度で圧迫し、歯冠角度を形成して食べ物が詰まりやすくなります。時間が経つと、第2大臼歯の虫歯や歯髄炎につながる可能性があります。それほど深刻でなくても、第2大臼歯の寿命に影響を与える可能性があります。 3. 親知らずを抜く? 親知らずは上記のような病気を引き起こす可能性があるため、ほとんどの専門家は将来のトラブルを避けるために親知らずを抜くことを推奨しています。親知らずが問題にならない人もいます。これは個人の生理的構造によって決まるため、このような人の場合は親知らずを抜く必要はありません。親知らずは三叉神経の枝に生えるため、適切に対処しないと口内の感覚や視力にさえ影響する可能性があります。成人の下顎骨と親知らずの歯根はすでに形成されているため、親知らずの抜歯手術には一定のリスクが伴います。糖尿病や心臓病などの患者様の場合、抜歯時に合併症を起こしやすいため、これらの方に対する親知らずの抜歯手術は慎重に行う必要があります。 |
推薦する
歯を全部抜くと顔が小さくなりますか?
歯が特に痛いと感じる場合は、必要に応じて抜歯する必要があります。これにより、痛みが完全になくなります...
胎児毒素を除去するために豆乳を飲むことは効果的である
周知のとおり、胎児毒素は乳児の健康に大きな影響を与えるため、胎児毒素をいかに除去するかという問題は、...
胃の痛みを和らげるにはどうすればいいでしょうか?時間内に解決することが重要です。
胃の痛みを和らげる方法胃の不調は食べることによって引き起こされる、とよく言われます。しかし、現在では...
便秘を治すニンジンの食べ方
ニンジンにはビタミンや食物繊維が豊富に含まれており、人体にとって優れた栄養補助食品です。便秘に悩む友...
夜寝ているときによく汗をかくのはなぜですか?
暑い夏が過ぎ、もう焼けつくような暑さに耐える必要はありません。夜寝るときに薄い毛布をかぶるだけで済み...
先天性気管支炎
気管支炎という病気は、主に気管支の保護に気を配らなくて気管支感染を引き起こすことで起こりますが、次の...
牛乳で洗顔するとどんな効果がありますか?
牛乳で顔を洗うことには多くの利点があります。例えば、牛乳は栄養が豊富で、酵素と呼ばれる成分が含まれて...
排卵後の体温はどのくらいですか?
女性は年齢を重ねるにつれて、自分の生理機能についてより深く理解するようになります。月経は女性の身体的...
黒砂糖にはエストロゲンが含まれていますか?
黒砂糖は日常生活で非常に一般的なもので、用途も多岐にわたります。黒砂糖を定期的に飲むことも、人間の健...
使い捨てマスクの正しい着用方法は何ですか?
使い捨てマスクは非常に一般的に使用されていますが、毒性の高い物質にさらされたり、発がん性物質に接触し...
朝シャワーを浴びるのは健康に良いのでしょうか?
お風呂に入るのは誰にとってもとても快適で、特に夜寝る前には最高です。熱いシャワーを浴びると、身体の疲...
鼻炎の場合、生理食塩水で1日に何回鼻を洗えばいいですか?
鼻炎はウイルス、細菌、および一部の全身性疾患によって引き起こされ、鼻粘膜の充血、腫れ、および肥大を引...
多発性神経炎の症状は何ですか?
患者としては、多発性神経炎の症状に注意する必要があります。通常、感覚障害、運動障害、自律神経機能障害...
閉鎖面皰を時間内に除去する方法
閉鎖面皰も比較的よく見られるニキビの一種です。このタイプのニキビは、一般的に痛みや痒みはありませんが...
ハニーレモンソーダ?
炭酸水は私たちの日常生活で非常に一般的な飲み物であり、炭酸水は弱アルカリ性物質であり、ある程度胃酸を...