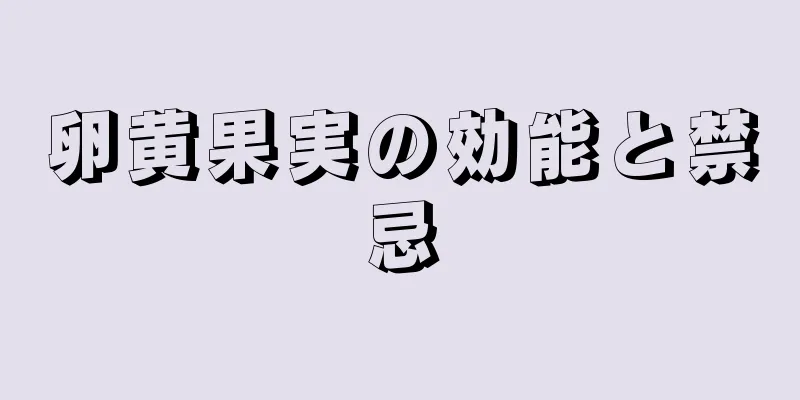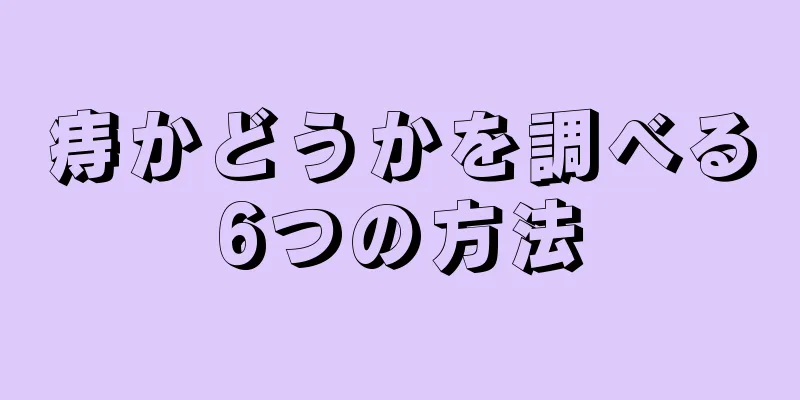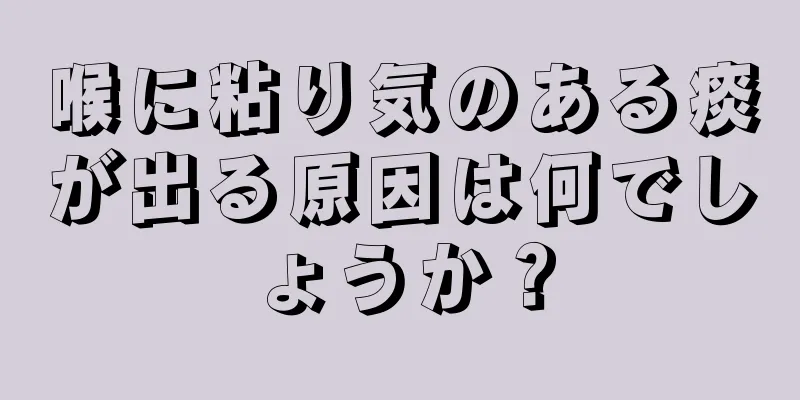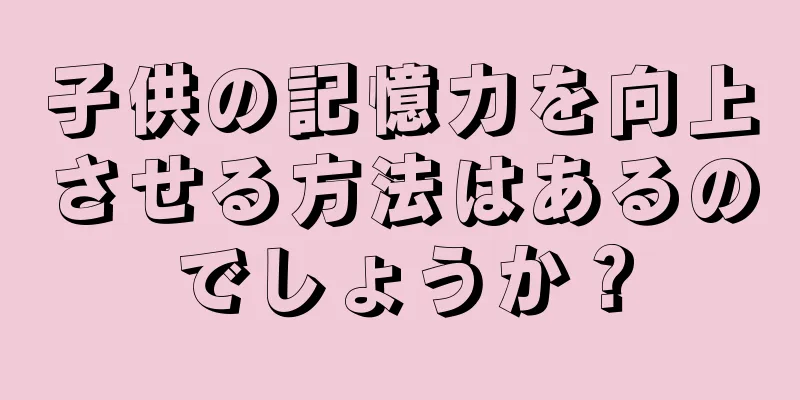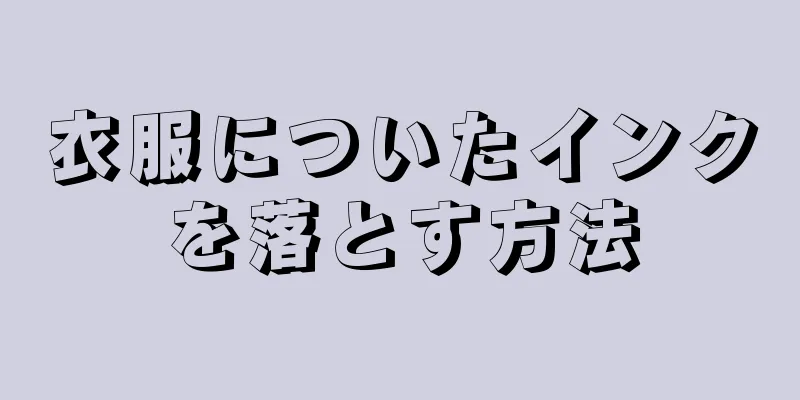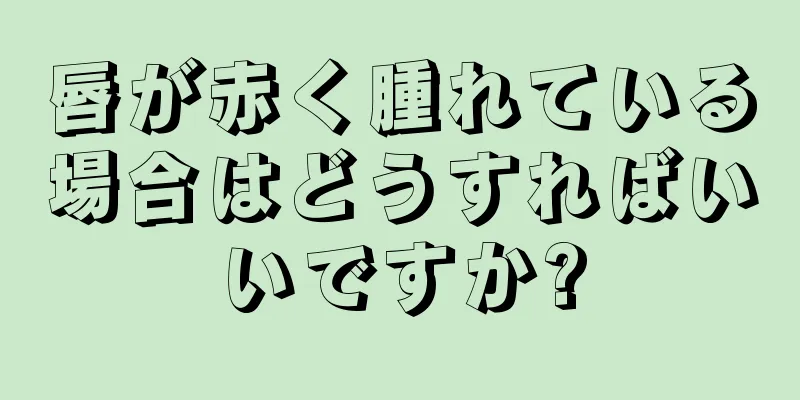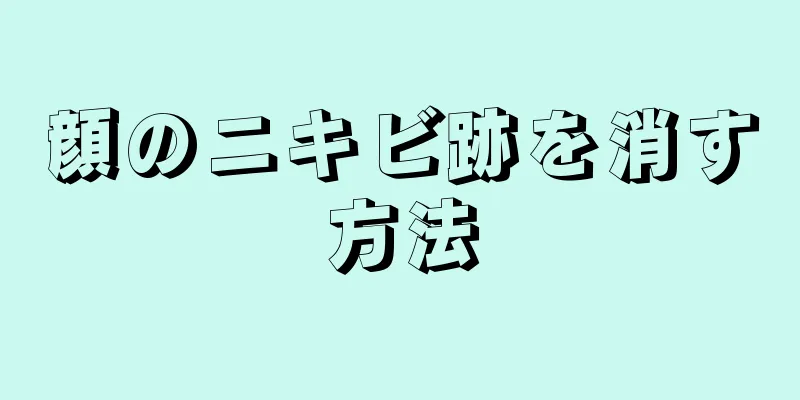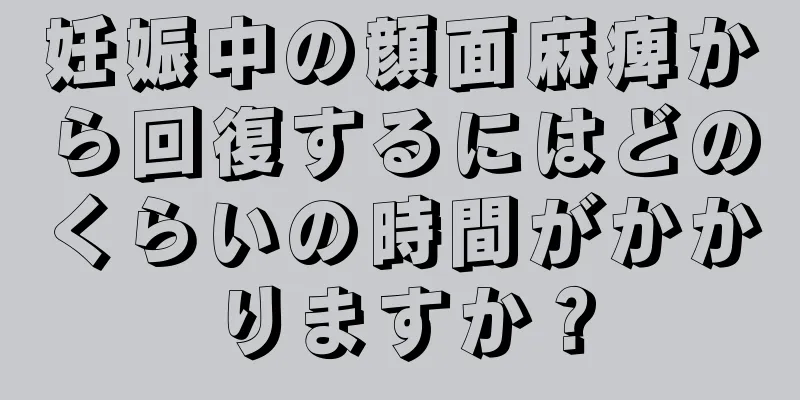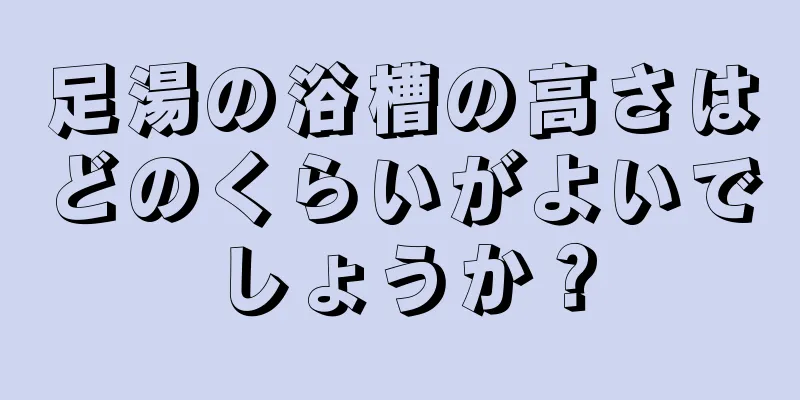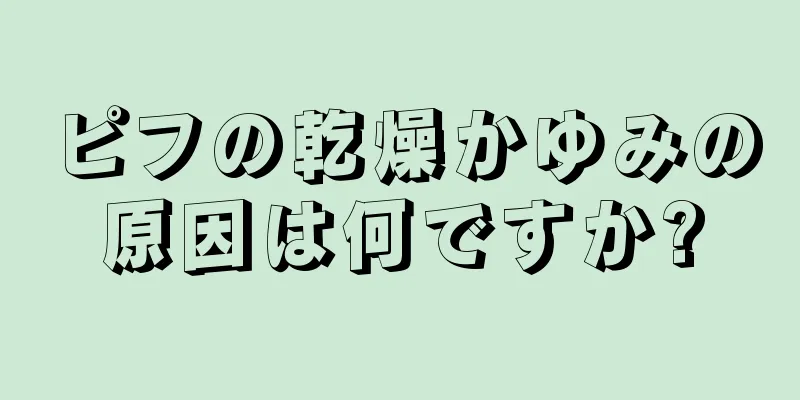脱出ロープの使い方
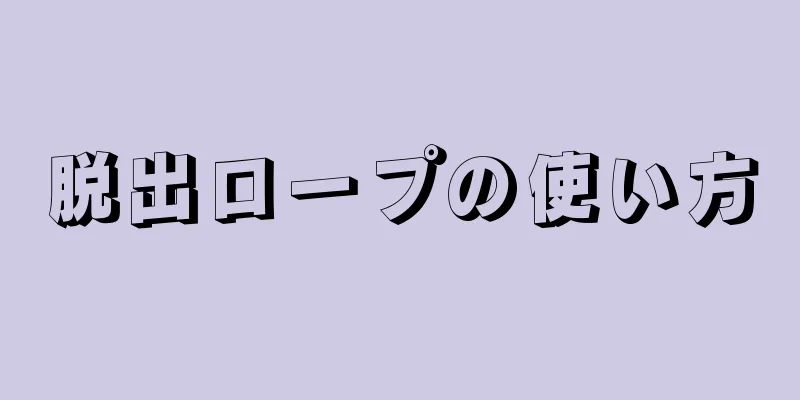
|
火災に遭遇したときは、二酸化炭素を吸い込まないように濡れタオルで口と鼻を覆い、自分自身を守る方法を知っておく必要があります。一般的に、火災時にはエレベーターは使用できません。階下に火災が発生し、階段から飛び出すことができない場合は、避難ロープを使用して身を守ることができます。ただし、避難ロープを使用する場合は、固定点を選択してロープを縛る必要があります。 1. 固定点を選択します。避難ロープまたは避難はしごの一方の端を頑丈な窓、テーブルの脚、暖房パイプなどの固い物体に固定し、下に引っ張って、自重に耐えられるかどうかを確認します。 2. 安全ベルトを腰、ウエスト、または脇の下に巻き付け、安全バックルを締めます。そして命綱を窓から階下へ投げ捨てました。 3. 保護手袋をはめて、両手で命綱を持ち、左足を窓枠に引っ掛け、右足で外壁を押し、体が安定したら左足を窓の外に出します。 4. 足を少し曲げ、足を壁に押し付け、腕を伸ばし、手を少し緩めて下を向き、命綱に沿って滑り降ります。 5. 地面に近づいたら、右腕を前に曲げ、ロープを締め、足を少し曲げて、つま先から着地します。 6. 1 人目が無事に着地した後、2 階の人が下階から上階へ安全ロープのもう一方の端を引っ張り、固定点に再度固定します。固定点の元の端は外して下階に投げ捨て、2 人目が引き続きそれを使って脱出できるようにします。 救命ロープを自分で操作できない高齢者や子供は、必ず大人の監督下で使用してください。保護者は高齢者や子供に安全ベルトを着用させ、救命ロープのもう一方の端を保護者が引き上げます。保護者は救命ロープをそっと放し、救助された人がゆっくりと地面に降りられるようにします。 脱出用ロープの使い方に関するこの記事を読んだ後、皆さんは自分の生活の中で脱出用ロープをどのように使うかが分かるはずです。生活の中で脱出用ロープをもっと有効活用したいなら、この記事で紹介した方法を使って自分自身を救うことができます。特に火災に遭遇したときは、固定された地点から脱出することを選択できます。 |
推薦する
ラカンカを水に浸すときに殻を剥く必要がありますか?なぜですか?
多くの友人は、羅漢果でお茶を作るときに殻を取り除いていますが、これは実際には間違いです。羅漢果の殻に...
家の中の湿度が高すぎる場合の対処法
家の中の湿度が高い場合は、適時に換気して、よく乾燥させる必要があります。結局のところ、湿気が多すぎる...
排尿後の胃の痛み
通常、排尿後に身体に不快な症状はありませんが、排尿後に腹痛を感じる人もいます。一般的に、この症状には...
心拍数57は正常ですか?
心拍数は人それぞれ異なり、年齢など多くの要因に関係しています。一般的に、心拍数が60〜100であれば...
目のかゆみは糖尿病の合併症ですか?
糖尿病自体が患者に大きな苦痛を引き起こす可能性があり、糖尿病には眼疾患などのいくつかの合併症も伴いま...
ニキビは吹き出物ですか?
ニキビと吹き出物の関係についてよく知らない人が多いです。ニキビと吹き出物は人間の顔の皮膚によく見られ...
誤って水銀を摂取した場合の対処法
水銀は有毒物質であり、化学元素の中で水銀の一般的な名称です。お子様が水銀を飲み込んでいないことに気付...
足を組んで瞑想するときの正しい座り方は何ですか?
若い人の多くは瞑想を好まないかもしれませんが、実は瞑想は非常に良い習慣です。特に今、人々の生活のペー...
額にたるみができる原因とは
映画やテレビドラマでは、「迎湯が暗い」「天頂が満ちている」という言葉がよく出てきます。ここで言う迎湯...
ふくらはぎのむくみの原因は何ですか?
体の特定の部分に浮腫が起こることがよくあります。ふくらはぎに浮腫がある場合、軽度の場合は動作に不快感...
塗料の臭いを素早く取り除く方法は?
最近では、家を購入する際、特に新婚住宅を購入する際、装飾を選択する人が増えています。装飾された家には...
妊娠検査紙の色が薄くなる
早期妊娠検査薬は、妊娠しているかどうかを検査するために使用される製品です。多くの女性が、妊娠している...
昆布には白い粘着質の物質が含まれています
市場で乾燥した昆布を見ると、白い粘着質の物質が付着していて、カビが生えていると思う人が多いようです。...
血液を補い、美容にも良いお粥の作り方は?
女性の場合、普段から食事を強化しなければなりません。特に月経期間中は、顔色が悪くなったり、体が疲れた...
アレルギー性鼻炎を予防する方法
アレルギー性鼻炎に悩まされている人は多いでしょう。そうなると、体に多大な害を及ぼします。特に予防が必...