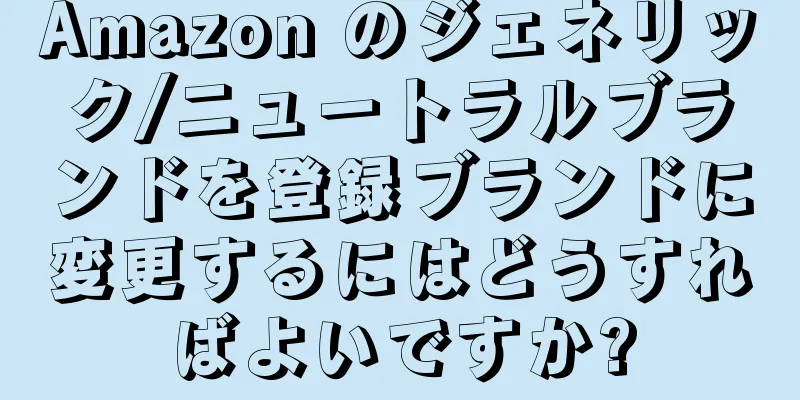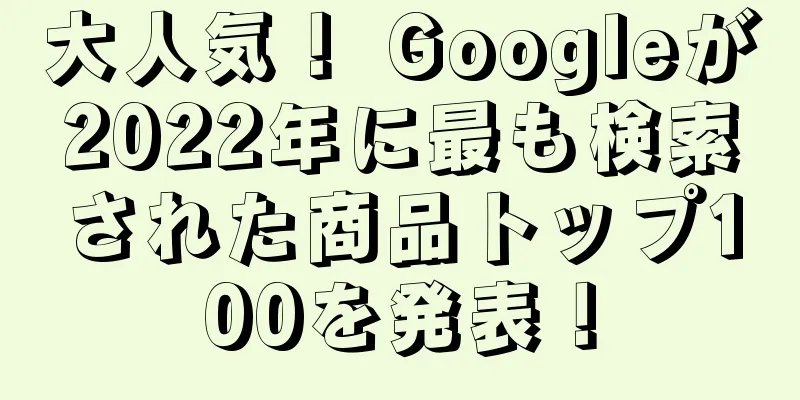胸椎損傷の治療法は何ですか?

|
胸椎は人体の胸部にある骨格器官で、脊椎の中央部に分布しており、人体にとって欠かせない部分です。胸椎は重力の支持と脊髄神経の支持という役割を担っており、人体にかかる衝撃力を緩和する役割も担っています。しかし、日常生活でカルシウム補給に注意を払わなかったり、運動中に胸椎が損傷したりすると、人体に大きな悪影響を及ぼし、喘息、呼吸困難、肺水腫、心筋梗塞などを引き起こす可能性があります。次に、胸椎損傷の治療について紹介します。 胸椎の概念 1.人間の胸椎は12個あります。 2.椎体は上から下に向かって次第に大きくなり、断面はハート型で、両側面の上端と下端にはそれぞれ上下の肋骨溝があり、肋骨頭と接合しています。 p2) 横突起の末端の前には、肋骨結節と接合する横溝がある。 3.第1胸椎および第9胸椎より下の胸椎の肋骨陥凹は非典型的である。 4.関節突起の関節面はほぼ冠状位置にあり、上関節突起の関節面は後方を向き、下関節突起の関節面は前方を向いています。 5.棘突起は長く、後方および下方に傾斜しており、隣接する棘突起は重なり合って配列されています。 対応する疾患 第一胸椎 食道炎、食道の腫れと痛み、喘息、呼吸困難、気管炎、胸膜炎、手の冷え、指の関節の痛み。 第二胸椎 不整脈、心筋梗塞、心筋炎、心内膜炎、心筋肥大、動脈硬化、心機能障害、高血圧。 第三胸椎 結核、肺炎、肺気腫、肺水腫、肺動脈狭窄、ショック、胸膜炎、気管炎。 第4胸椎 黄疸、胆汁過多、胆石、動脈硬化、神経衰弱、うつ病、白髪の早期化。 第5胸椎 高血圧、低血圧、循環障害、肝機能低下、肝火性黄疸、肝炎。 第6胸椎 各種胃炎、胃酸分泌障害、消化不良、胃潰瘍、胃がん、胃運動不全など。 第七胸椎 各種消化酵素の異常分泌、糖尿病、低血糖、十二指腸潰瘍など。 第8胸椎 貧血、脾臓肥大、神経過敏、息切れ、麻疹、減量困難な肥満、過度の発汗および寝汗、睡眠時の夢見心地。 第9胸椎と第10胸椎 排尿時の痛み、腎炎、腎不全、尿毒症、動脈硬化、慢性疲労、腰痛、腎臓病。 第11胸椎 皮膚障害。 第12胸椎 吸収障害、栄養失調、腸炎、腹痛、免疫力の低下。 胸部脊髄損傷と高次対麻痺を併発した場合、西洋医学の手術では脊柱管の直径を修復するだけで、神経は再び損傷し、治療の使命は完了しますが、損傷した神経は依然として麻痺とショック状態にあります。無力であり、回復を待つことしかできません。このプログラムでは、自己修復に加えて神経機能の回復も治療できます。損傷した神経が長期間にわたって虚血性変性を起こした場合、この病気からの回復は望めません。 治療の選択肢 1.損傷した神経に十分な血液が供給されるように、漢方薬を使用して脊髄の血液循環を強化・改善します。 2. 伝統的な中国医学と西洋医学を組み合わせて神経を養います。 3.神経再生薬を使用して、麻痺してショック状態にある損傷した神経を刺激し、活性化します。 4.ステントの自律的な機能訓練により、機能再建を実現し、最適な早期回復を達成できます。 |
推薦する
足首が腫れる原因は何ですか?
日常生活において、両足首の腫れは多くの人によく見られる症状です。一般的に、足首の外傷により、足首が腫...
目の下に2本の斜めの線がある場合、それは何を意味しますか?
人間の体の構造は、一回多く打つと多すぎる、一回少なく打つと少なすぎる、といった感じで、すべてがちょう...
C型肝炎の感染経路
C 型肝炎もウイルス性肝炎の一般的なタイプです。肝臓に大きな損傷を与える可能性があり、感染力も非常に...
人体のどの部分が最初に老化するのでしょうか?
人体は多くの部分で構成されています。誰もがある程度理解していると思いますが、人体のどの部分が最初に老...
女性にとってビタミンB2を摂取することの利点は何ですか?
ビタミンは人体に欠かせない栄養素です。人体にビタミンが不足すると、多くの病気につながります。人体がビ...
髪の毛が抜けると何が問題なの?
現実の生活では、多くの人が髪の毛が部分的に抜ける傾向があり、これには多くの理由があります。一般的に、...
定期的な尿検査には朝の尿が必要ですか?
初めて病院で尿検査を受ける人の多くは、経験も知識もあまりないので、朝一番の排尿を使わなければならない...
顔にアレルギーがあり、黄色い分泌物が出たらどうすればいいですか?
顔のアレルギー反応は通常、経口抗アレルギー薬による治療が必要ですが、症状を改善するために抗感染薬を使...
赤く腫れ、かゆみ、痛みを伴う皮膚疾患は夏に治療する必要があります
皮膚病は日常生活で最もよく見られる病気の一つです。病気になると、皮膚に赤み、腫れ、かゆみ、痛みなどの...
右頬のニキビの治療法
顔にニキビができるととても困りますが、漢方医学の観点から見ると、ニキビが現れる場所によって、人体のさ...
鉄分を摂取する最も早い方法
人生において、鉄分不足は非常に一般的な現象です。ほとんどの人は貧血に悩まされます。実際、貧血の原因は...
なぜ突然口が腫れたのでしょうか?
こうした患者が病院に行って診察を受けるとき、突然病気になったと医師に伝えます。実際、突然の病気は一般...
白斑皮膚疾患の一般的な原因は何ですか?
皮膚に白い斑点が現れ、拡大する傾向があります。一般的に言えば、これは白斑です。白斑は比較的頑固な皮膚...
脂肪注入の効果はどのくらい持続しますか?
美容を愛するあまり、さまざまな美容整形手術法で容姿を変える人がたくさんいます。現在、多くの美容整形手...
骨盤閉鎖術とは何ですか?
女性の生命の臓器は骨盤であるため、骨盤の健康は胎児の健康に直接影響します。同時に、骨盤はさまざまな婦...