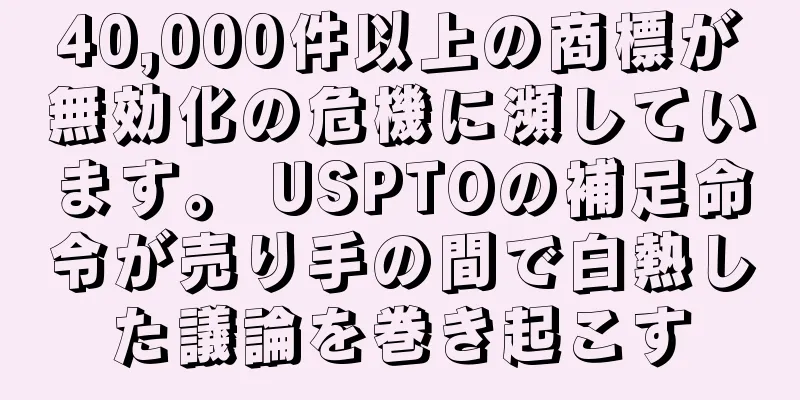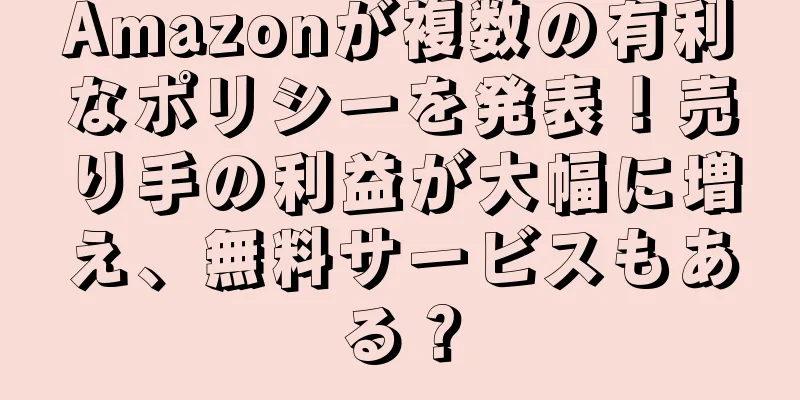食中毒緊急対応 食中毒の対処方法

|
食中毒は日常生活でよく見られる症状ですが、特に豆が熟す季節には食中毒がさらに多く発生します。では、人体に食中毒が発生した場合、どのような応急処置を行うべきなのでしょうか?ほとんどの人はこれを本当に理解していません。実は、人体における食中毒の緊急対応策は3つあります。1つ目は、嘔吐による治療です。 1. 嘔吐による治療 特定の食品を食べて1~2時間以内に中毒が判明した場合は、嘔吐による治療が考えられます。① 200ミリリットルのお湯に20グラムの塩を溶かし、一度に200ミリリットルの塩水を患者に飲ませます。患者が嘔吐しない場合は、さらに数回飲ませます。 ② 生姜100グラムをジュースにしてつぶし、生姜ジュースを200mlのお湯に注ぎ、患者に生姜ジュースを一度に飲ませます。患者が嘔吐しない場合は、さらに数回飲ませることができます。また、箸や指を使って患者の喉を刺激し、嘔吐を誘発することもできます。 2. 下剤による治療 患者が中毒食品を食べて2〜3時間以上経過しており、精神状態が比較的良好な場合は、下剤法で治療することができます:①ダイオウ30グラムを水で煎じ、患者にその液体を一度に飲ませます(この方法は高齢者や虚弱者には使用できません)。②ミョウバン20グラムを沸騰したお湯で煎じ、患者に一度に飲ませます。③センナの葉15グラムを水で煎じるか、沸騰したお湯で煎じ、患者に飲ませます。 3. 解毒による治療 患者が腐った魚、エビ、カニなどの食品を食べて中毒になった場合、解毒には次の方法を使用できます:①酢100mlを冷水200mlで薄め、患者に一度に飲ませます。②シソ30グラムと生の甘草10グラムを水で煮て、患者に一度に飲ませます。患者が腐った飲み物によって中毒になった場合、新鮮な牛乳やその他のタンパク質を含む飲み物を摂取することで解毒することができます。 食中毒患者が上記の方法で応急処置を行った後、再度病院に行って検査を受けるのが最善であることに留意してください。特に重度の中毒の場合は、できるだけ早く病院に行って治療を受ける必要があります。 さらに読む: 細菌性食中毒 食中毒は、大量の生きた細菌や細菌毒素を含む食品を食べることで起こります。最も一般的なタイプの食中毒です。このタイプの食中毒には、次の 3 つの特徴があります。 (1)抵抗力が低下している人々:病人、高齢者、子供などは細菌性食中毒にかかりやすく、発症率が高く、急性胃腸炎の症状も重くなりますが、このタイプの食中毒の死亡率は低く、回復も良好です。 (ii) 通常は明らかな季節性があり、暑い季節に発生することが多く、通常は5月から10月が最も多く発生します。一方で、気温が高くなると細菌の繁殖に好条件が生まれ、他方では、この期間中は人体の防御力が低下して感受性が増すため、細菌性食中毒が頻繁に発生します。 (3)細菌性食中毒を引き起こす食品:主に肉、魚、牛乳、卵などの動物性食品ですが、残りご飯、餅、発酵麺などの植物性食品も少数あります。 |
>>: 水銀中毒にはどう対処すればいい?治療法は3つあることが判明
推薦する
よもぎ足湯の効能とは
ヨモギは皆さんもよくご存知だと思います。漢方灸によく使われています。実は、ヨモギはお灸だけでなく、足...
関節液貯留を治療するには?
関節液が溜まる部位は主に膝関節です。膝関節は、頻繁に歩くことで摩耗しやすくなります。特に、膝関節の間...
肌が乾燥してアレルギーを起こしている場合はどうすればいいですか?
皮膚は人体最大の器官で、全身を覆っています。人体にとって皮膚は地球にとってのオゾン層のようなものであ...
目の疲れを和らげるアイパッチの使い方
目は心の窓ですが、私たちの生活環境では、パソコンや携帯電話に向き合うことが多いため、目の疲れが起こり...
寝るときに髪を内側にまとめる方法
ヘアスタイルは女の子にとってとても重要です。素敵なヘアスタイルは、あなたを一気にワンランク上の存在に...
グアシャを受けるべきではない6つのタイプの人々
スクレイピングには多くの利点がありますが、スクレイピングを実践すべきでない人が 6 種類います。 1...
胃がんの初期症状は何ですか?胃がんの初期段階ではどのような信号が送られますか?
胃がんの発症年齢のピークは50~80歳だが、近年は胃がんの発症年齢が若年化する傾向にあると徐崇安氏は...
唇に色素沈着がある場合はどうすればいいですか?
唇が黒く生まれつきの人もいますが、美容は好きだけど化粧品を買うお金がない人もいます。しかし、一部の粗...
緑豆泥マスクの効果と機能は何ですか?
緑豆といえば、熱を消し、夏の暑さを和らげる効果がある緑豆を思い浮かべる人が多いでしょう。緑豆は夏に欠...
魚のフライを美味しく簡単に作る方法
揚げ物は多くの人にとって非常に魅力的です。揚げられる食べ物はたくさんあります。その中でも、魚は揚げ物...
親知らずを抜いてからどれくらい経ったらシャワーを浴びることができますか?
親知らずは痛みをもたらすだけでなく、通常の食事にも影響を及ぼします。親知らずを抜いた後、痛みを感じる...
性格を変える方法
人によって性格は異なり、性格は変えられますが、すべての人の性格には良い点と悪い点があることは多くの人...
歯のインレーは何年持ちますか?
歯科用インレーは歯の欠陥を修復するために使用されます。虫歯や歯の破損があった場合、医師は歯の詰め物と...
目の痛みの原因は何ですか?
今日の科学技術の急速な発展により、毎日携帯電話を見たり、仕事でコンピューターを使用したりしている人が...
いつも眠いのですが、何が起こっているのでしょうか?
病気になると、体がだるくなり、何もしたくなくなります。眠いのに眠れないこともよくあります。眠気やエネ...