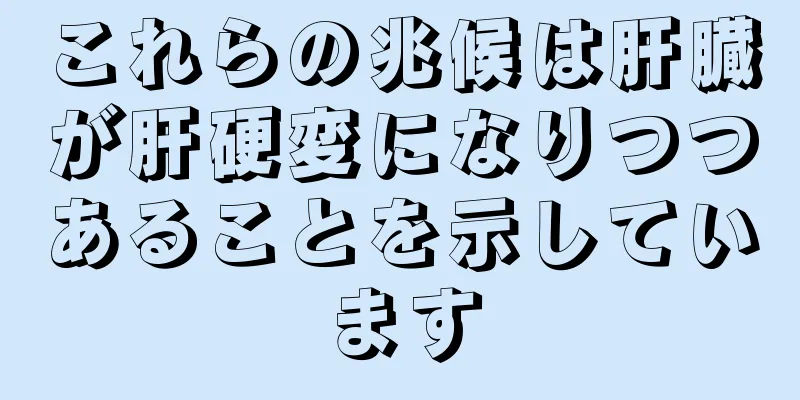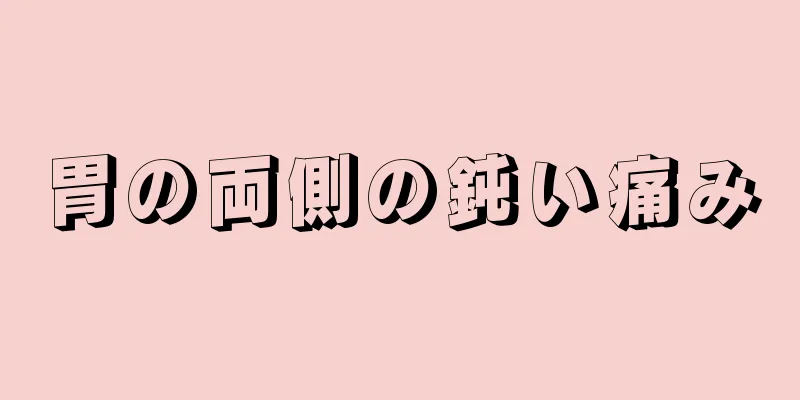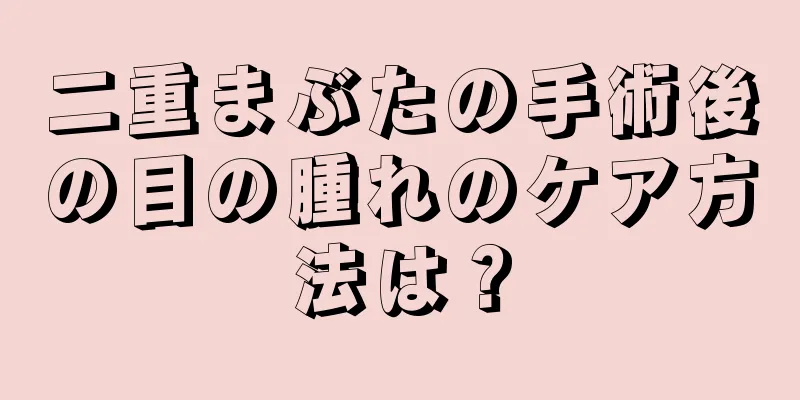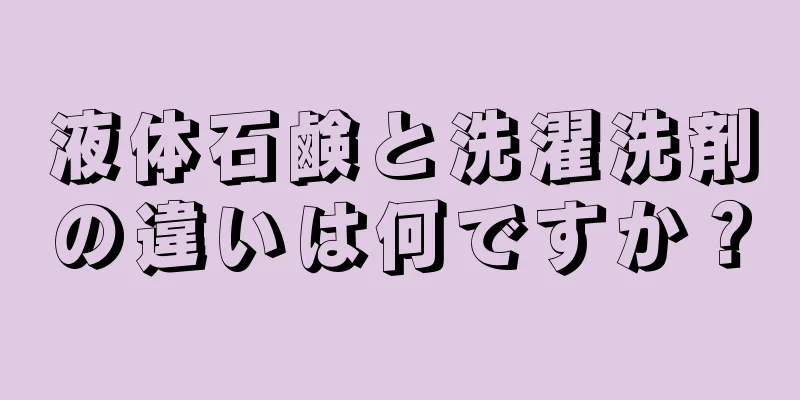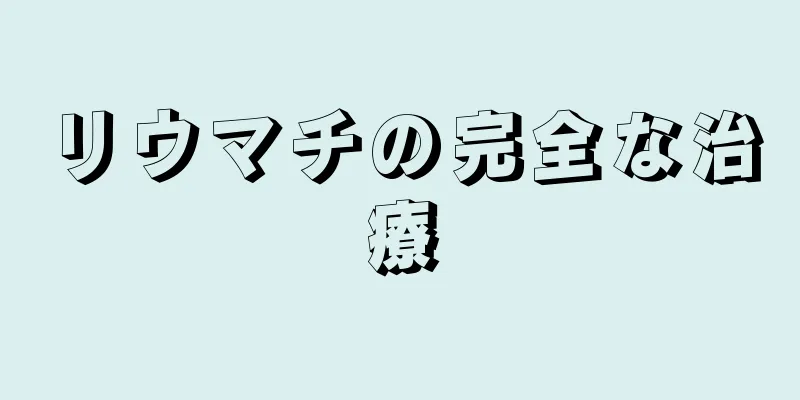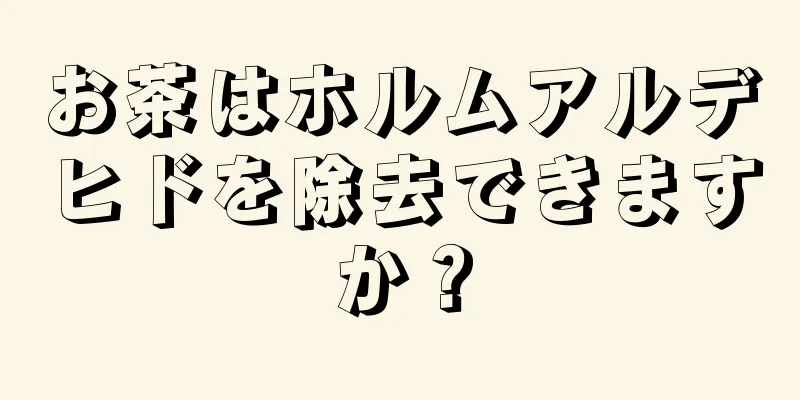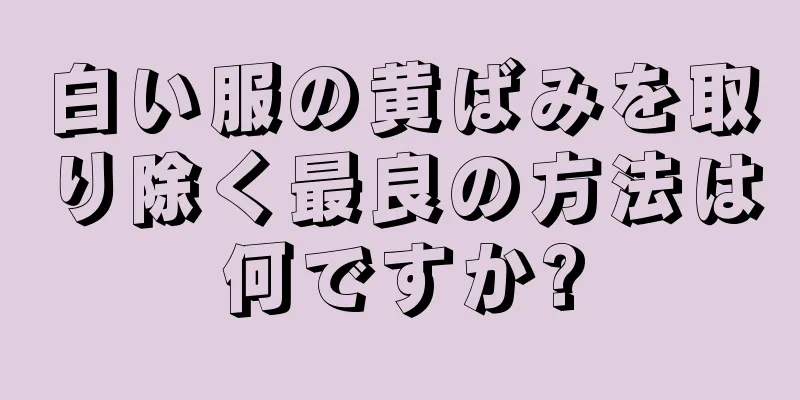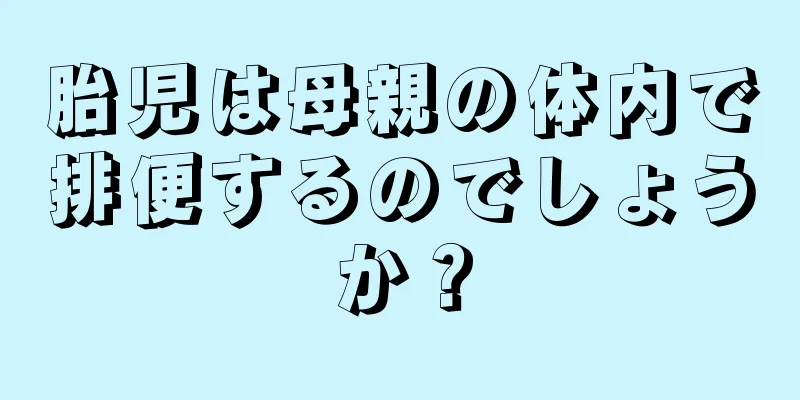爪が割れてしまったらどうすればいいですか
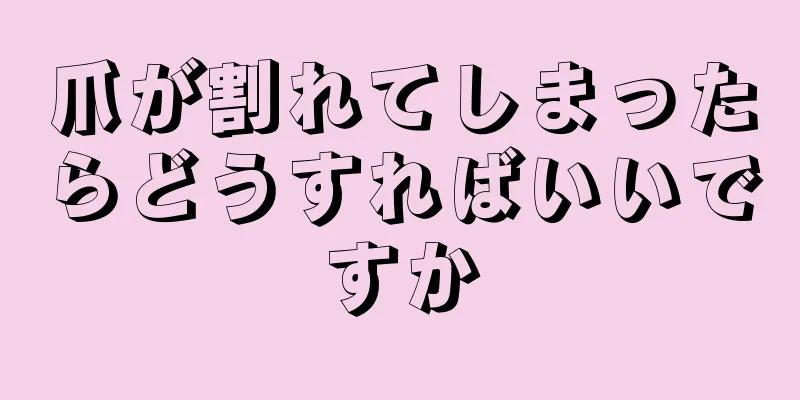
|
爪は硬いように見えますが、外部からの衝撃や不適切なケアにより割れやすくなります。また、洗剤や化学薬品を長期間使用したり、病気や体内の水分不足に悩まされたりすると、爪が折れやすくなります。では、折れた爪を修復するにはどうすればいいのでしょうか?以下、関連する知識をご紹介します! 1. 爪が折れやすい原因の分析 1. 洗剤や化学薬品によるダメージ 爪の端が折れたり剥がれたりしやすく、家事をしているときに右手の最初の3本の指によく起こります。食器を洗ったり、手で洗濯をしたりすると、熱いお湯と洗剤の複合効果で爪が傷つくことがよくあります。 2. 病理学的影響 貧血(特に鉄欠乏性貧血)、ビタミン欠乏、湿疹、骨粗しょう症、爪白癬の感染、および一部の先天性疾患により、ケラチンの構造が変化し、爪の硬さに影響が及び、爪が割れやすくなります。 3. 水分の損失 乾燥した環境では、爪は乾燥して脆くなり、割れやすくなります。適切な水分量を維持するために、爪には水分を閉じ込めて過剰な蒸発を防ぐのに十分な脂質が必要です。水、特に熱い水に繰り返し触れると、爪の脂質含有量が減少し、適切な保湿機能が損なわれます。 2. 割れた爪を修復するための具体的な手順 ステップ 1: シルクテープを小さな正方形に切り、割れた爪に貼り付けます。上部に少しスペースを残してください。 ステップ2: テープに専用の接着剤を塗ります。 ステップ 3: 接着剤が乾く前に、ネイル リペア パウダーを薄く振りかけます。爪の損傷の程度に応じて、上記の手順を 2 ~ 3 回繰り返します。 ステップ 4: 完全に乾いたら、爪やすりを使って余分なテープを切り取ります。 3. 科学的な鎧の手入れ習慣 1. 手を優しく洗い、硬い毛のブラシで爪を引っかいたり、爪で硬いものを乱暴にこすったりしないでください。爪がもろくなり、爪が丸まって爪床から離れてしまいます。 2. 食事にタンパク質を補給する。爪はタンパク質でできています。爪の下部に白い横線が現れた場合は、タンパク質不足の可能性があります。豆類、種子類、ナッツ類、卵、肉類をもっと食べる必要があります。 3. 定期的に爪を切ってください。爪の端が滑らかになるまでこすって、楕円形に切りそろえてください。爪が尖りすぎると強度が弱まり、折れやすくなります。 4. マニキュアを頻繁に塗らないようにしましょう。爪の表面には歯の表面のエナメル質に似た物質の層があり、爪を腐食から守ることができます。マニキュア中に爪の表面層を削ると、指の保護層が失われ、酸性またはアルカリ性物質による腐食に対する耐性が失われます。そのため、頻繁にマニキュアをすると爪が折れたり、爪が黄色や黒に変色したりする可能性があります。 5. 寒くて乾燥した天候では、皮膚の他の部分と同様に、爪の水分が急速に失われます。マニキュアやマニキュアを塗る人もよくいます。爪に栄養と水分が適時に補給されないと、爪は乾燥しやすく、黄色くなり、もろくなり、割れやすくなります。 |
推薦する
一般的な魔法瓶カップにミルクは入りますか?
魔法瓶カップは一般的に水を飲むために使われますが、ミルクを作るためにも使われる人が多いです。実は、魔...
ダイエットのためのツボ糸埋め込み法とは?
人々の生活水準が向上するにつれて、肥満患者の数が増加しています。肥満は良いことではないため、肥満患者...
越境購買プラットフォームが突然襲撃された! 30人が逮捕され、何百万もの荷物が押収されました!
アマゾンが3月26日に2023年ブランド保護レポートを発表したことが判明した。 2023年、アマゾン...
コンタクトレンズは片目だけ
最近では近視のため眼鏡をかけるのが一般的ですが、美容上の理由からコンタクトレンズを選ぶ人もいます。確...
午後になるといつも頭痛がする場合はどうすればいいでしょうか?
午後に頭痛がするが、他の時間帯は正常である場合、それは過労による緊張性頭痛である可能性が高いです。緊...
重要な新しい規制!スキャン番号の真実を明らかにすると、Amazon の販売業者は毎年 2 回目の審査を受けることになるのでしょうか?
先月末から、多くのAmazonセラーに対して新たな一連の番号スキャンが実施されている。複数の関係者か...
真空カッピングの利点は何ですか?
カッピングは我が国の伝統的な中国医学療法の一つで、安定した治療効果と副作用の少なさで高く評価されてい...
ヘモグロビン濃度が高くなる原因は何ですか?
血液は人間の生存の基盤です。血液はさまざまな臓器の正常な機能に必要な栄養素を供給します。血液にはヘモ...
夜間に体はどのように解毒するのでしょうか?
最近では、ナイトライフが充実し、昼夜のスケジュールが逆転する人も多く、顔色の悪化、ニキビ、肌のたるみ...
甲状腺機能亢進症を伴う妊娠とはどのようなものですか?
甲状腺機能亢進症を伴う妊娠とは、妊娠中に妊婦が甲状腺機能亢進症などの病気を発症することを意味します。...
首に発疹が出る原因は何ですか?
あせもや湿疹などがあるとき、首に赤い発疹が現れることがよくあります。単なる発疹だけでは、問題を説明す...
緊急! BrexitによりEUの道路が通行止めに!
外国メディアは、ブレグジットの影響で荷物の5分の1に間違いや不備があり、DPDはアイルランド共和国へ...
リンパ節ニキビの原因は何ですか?
体にニキビがあると、とても不快な気分になります。特に、体の特定の部分にニキビが生えると、生活に不便が...
パパイヤは性的能力を高めますか?
パパイヤは生活の中でよく見かける果物です。栄養が豊富で、パパイヤを食べるのが好きな人もたくさんいます...
沸騰したお湯に白酢を加えるとどんなメリットがあるのでしょうか?
白酢を使ってお湯を作ると、一定の健康効果があります。まず、消化を促進する効果があり、腸内の便の排泄を...