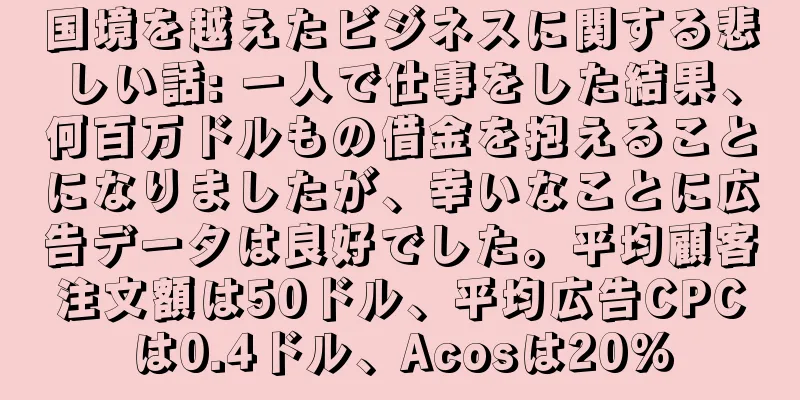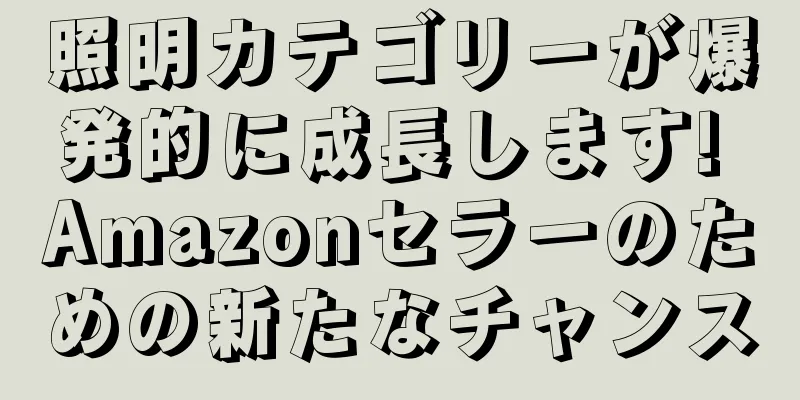五臓六腑と六腑の関係

|
人間の体には5つの内臓と6つの腸があります。5つの内臓と6つの腸は、主に人間の体の主要な臓器を指します。したがって、五臓六腑のうちどれか一つでも欠けると、人体に異常が生じます。五臓六腑と六腑は存在形態が大きく異なりますが、実は両者の関係は切り離せないものです。では、五臓六腑と六腑の関係は何でしょうか? 五臓六腑の関係 「臓」は心臓、肝臓、脾臓、肺、腎臓などの構造を持つ固形臓器を指します。「附」は小腸、胆嚢、胃、大腸、膀胱などの中空の容器を指し、それぞれ五臓に相当します。また、人間の胸腔と腹腔は上焦、中焦、下焦に分かれており、これが六腑です。 汚いと汚いの関係 1. 心臓と肺:心臓は血液を制御し、肺は気(エネルギー)を制御します。人体の臓器や組織の機能活動の維持は、栄養素を運ぶ気と血の循環に依存しています。血液の正常な循環は心臓によって制御されますが、肺気によって促進されなければなりません。肺に蓄積された生命エネルギーは、体全体にスムーズに流れるために、心臓の経絡に注入される必要があります。 2. 心臓と肝臓:心臓は血液循環の原動力であり、肝臓は血液を貯蔵する重要な臓器であるため、心臓の血液が活発であれば、肝臓の血液貯蔵量も豊富になり、腱や静脈に栄養を与えるだけでなく、人体の手足や骨の正常な活動を促進することもできます。心血の不足により肝血が不足すると、腱に血液が栄養を供給できなくなり、腱や骨の痛み、手足のこむら返り、けいれんなどの症状が現れます。例えば、肝鬱が火に変わると、心臓に悪影響を及ぼし、落ち着きのなさや不眠などの症状を引き起こすことがあります。 3. 心臓と脾臓:脾臓によって変化した精気は、血液の循環によって体全体に行き渡る必要があります。そして、心血は脾臓によって吸収され伝達される水と穀物の精気に依存しなければなりません。一方、心臓は血液を制御し、脾臓は血液を調節します。脾臓が正常に機能している場合にのみ、血液を調節することができます。脾臓が弱いと、経絡を通って血液が流れなくなる可能性があります。 4. 心臓と腎臓: 心臓と腎臓は相互作用し、互いに制限し合い、生理機能の相対的なバランスを維持します。生理的条件下では、心の陽は下がり続け、腎臓の陰は上がり続け、上部と下部が交差し、陰陽が互いに補完し合います。これを「心腎互作用」といいます。病的な状態では、腎陰が不足して心臓に供給できない場合、心臓陽が過剰に活動し、両者のバランスが崩れ、「心腎不和」と呼ばれます。 5. 肝臓と脾臓:肝臓は血液を貯蔵し、脾臓は水と穀物の精気を輸送して変換し、血液を生成する役割を担っています。例えば、脾臓の虚弱は血液の生成に影響を及ぼし、肝血不足、めまい、視力低下などを引き起こす可能性があります。肝臓は平穏を好み、鬱滞を嫌います。肝気が滞って脾臓を侵すと、腹痛や下痢などが起こることがあります。 6. 肝と肺:肝経は脂肪を通り、肺まで流れます。両者は互いにつながっています。肝気は上昇し、肺気は下降します。これは人体の気の上昇と下降に関係しています。肝気が逆流し肺が下降できない場合は胸の圧迫感や息切れなどの症状が現れることがあります。肝火が肺を侵すと、胸部や脇腹の痛み、乾いた咳、痰に血が混じるなどの症状も現れることがあります。 7. 肝臓と腎臓:腎臓は精を蓄え、肝臓は血を蓄えます。肝血は腎精の栄養に頼る必要があり、腎精は肝臓によって絶えず補充される必要があります。この2つは相互に依存し、互いに支え合っています。腎精が不足すると肝血不足に陥ります。逆に、肝血不足は腎精の生成に影響を及ぼす可能性があります。腎陰が不足し、肝臓が栄養を失うと、肝陰虚を引き起こし、めまい、耳鳴り、震え、しびれ、けいれんなどの肝陽亢進または肝風の症状を引き起こします。 8. 肺と脾臓: 脾臓は食物と水の精気を肺に運び、そこで肺で吸い込んだ精気と結合して総気(肺気とも呼ばれる)を形成します。肺気の強さは脾臓の精気輸送能力と関係があり、脾臓の気が強ければ肺気も豊富です。脾虚が肺に影響を及ぼすと、食欲不振、怠惰、便秘、咳などの症状が現れることがあります。 「脾臓を補って肺を利する」という方法は、臨床治療でよく用いられます。例えば、慢性の咳に悩まされていて、吐き出しやすい薄い白い痰が多く、倦怠感や食欲不振がある場合、症状は肺にあるものの、病の根源は脾臓にあり、「脾を強め、湿を乾かし、痰を解く」方法が効果的です。 「肺は痰を蓄える臓器であり、脾臓は痰の源である」という言葉は、脾臓と肺の関係を反映しています。 9. 脾臓と腎臓:脾臓の陽は腎臓の陽の温かさと栄養に依存して、輸送と変換の役割を果たします。腎陽が不足すると脾陽が不足し、輸送と変換の機能不全を引き起こし、夜明け下痢や消化不良などの症状を引き起こします。逆に、脾陽が不足すると腎陽も不足し、腰冷えや浮腫などの症状が現れます。 10. 肺と腎臓: 肺は水路を下降させて調節し、水が腎臓まで流れるようにする役割を担っています。腎臓は水分と体液を制御し、腎陽の蒸発により最も純粋なものが肺に戻り、脾陽の輸送と変換に依存して水分代謝の機能を完了します。肺、脾臓、腎臓のいずれかの機能不全は、水分の貯留を引き起こし、浮腫につながる可能性があります。肺は呼吸を司り、腎臓は空気を取り入れる役割を担っています。この2つの臓器は協力して体内の気の上昇と下降を調節します。 臓腑と臓腑の関係 内臓と臓腑は内外において互いに協力し合い、一つの内臓は一つの臓腑と対応しています。内臓は陰であり、内側にあり、臓腑は陽であり、外側にあります。内臓の内と外は経絡によってつながっており、つまり内臓の経絡は内臓につながり、内臓の経絡は内臓につながっています。経絡は互いにつながって相互作用するため、内臓と内臓は互いに影響を及ぼし、互いの病理変化を伝達することができます。 内臓の関係は、心臓と小腸は外と内、肝臓と胆嚢は外と内、脾臓と胃は外と内、肺と大腸は外と内、腎臓と膀胱は外と内、心嚢と三焦は外と内です。 1. 心臓と小腸:経絡はつながっており、相互に外と内にあります。心経の熱により口や舌に腐食が生じることがあります。心経の熱が小腸に伝わると、尿が短くて色が濃くなったり、尿道が痛んだりするなどの症状が出ることがあります。 2. 肝臓と胆嚢:胆嚢は肝臓に貯蔵され、内臓はつながり、経絡はつながり、内と外を構成します。胆汁は肝臓から分泌されます。肝臓の分泌が異常であれば、胆汁の正常な排泄に影響を及ぼします。逆に、胆汁の排泄異常は肝臓に影響を及ぼします。そのため、黄疸、脇腹の痛み、口の中の苦味、めまいなど、肝臓と胆嚢の症状が同時に現れることがよくあります。 3. 脾臓と胃:性質上、脾臓は乾燥を好み湿気を嫌い、胃は湿気を好み乾燥を嫌います。脾臓は上昇を司り、胃は下降を司ります。生理機能の面では、胃は水と穀物の海であり、消化の役割を担っています。脾臓は胃の体液を循環させ、輸送と変換の役割を担っています。両者は乾湿を補い合い、盛衰を調整し、胃と脾臓によって変化し、互いに奉仕し合い、対立と統一の矛盾した運動を形成し、食物と水の消化、吸収、伝達の働きを共に完成させます。 胃気がスムーズに下降し、胃気が調和して下降すると、食べ物や水も下降できるようになります。脾臓より上の動作はスムーズで、脾臓のレベルが上昇し、微細物質を上方に輸送することができます。胃気が下がらずに上がれば、吐き気や嘔吐などの症状が出やすくなります。脾気は上昇せず下降するため、慢性下痢、肛門脱、子宮脱などの症状を引き起こしやすくなります。脾臓と胃は生理的に密接に関連しており、病理的にも相互に影響を及ぼしているため、臨床診療では一緒に議論され、一緒に治療されることがよくあります。 4. 肺と大腸:これらは経絡によってつながっており、相互に外と内にあります。肺の気が下降すると、大腸の気は妨げられず、伝導機能を果たすことができます。逆に、大腸がスムーズな伝導を維持すれば、肺の気は清められ、下降することができます。例えば、肺気が停滞し下降機能が失われると、大腸伝導障害や便秘を引き起こす可能性があります。逆に、大腸伝導ブロックは肺の下降機能の異常を引き起こし、息切れ、咳、喘息を引き起こす可能性があります。たとえば、治療では、肺に実際に熱がある場合、大腸から熱を排出できるように大腸をドレナージすることができます。逆に、大腸が詰まっている場合は、肺の気の流れを促進し、大腸の気の流れを良くすることができます。 5. 腎臓と膀胱: 経絡はつながっており、互いの外側と内側になっています。生理学的には、一方が水器官、他方が水臓であり、両者が協力して水分代謝のバランスを維持します(主に腎臓)。腎陽の蒸発により水分が膀胱に浸透し、膀胱は腎陽の助けを借りて、自らの機能で尿を排泄します。病理学的には、腎陽が不足すると膀胱の機能が弱まり、頻尿や夜尿症を引き起こします。膀胱の湿気や熱は腎臓に影響を及ぼし、腰痛や血尿などを引き起こします。 6. 心包と三焦: 経絡は相互に連結しており、相互に外経と内経になっています。例えば、臨床の現場では、発熱時の湿熱が組み合わさって三焦の停滞を引き起こし、胸の圧迫感、体の重苦しさ、尿量減少、軟便などの症状が現れ、病気が気の段階にあることを示しています。進行を止めなければ、温熱の病因は気部から陰部に入り、三焦から心嚢に浸透し、昏睡やせん妄などの症状を引き起こします。 |
>>: マンゴーアレルギーで顔がかゆくなったらどうすればいい?
推薦する
メイクをした後も顔に毛が生えてくる
最近では、肌を滑らかに見せ、より元気に見えるように、女の子は外出前に化粧をすることが多いです。ただし...
離乳後、乳の張りが最も痛くなるのはどの日ですか?
産後の母親は長期間母乳で育てる必要があります。ある時点で、母親は断乳を選択します。断乳に関しては、突...
先天性心疾患
先天性心疾患の症状は比較的一般的であり、患者の体と心に多大な害をもたらします。先天性心疾患の治療法を...
農薬の誤判断がまた来る!アマゾンは数百万ドルの罰金を科せられた
過去2日間で、Amazonはカリフォルニア州農薬規制局(DPR)と和解合意に達し、 Amazonは最...
システムの誤判断?多数の二次アカウントが復旧しました! Amazonの仕組みは緩むのか?
2021年も残り2ヶ月となりました。今年を振り返ると、アカウント禁止措置が次々と押し寄せ、何百もの...
手のひらの皮がむける
毎年春と秋になると、何人かの友人の手のひらが剥がれてしまいます。皮膚が老化するにつれて、活力を失った...
蜂蜜は目の下のクマを消すことができますか?
最近は夜更かしすることに慣れた人が増えています。仕事や勉強の課題が終わっていないために夜更かしする人...
液体ベビーパウダーは良いですか?
ベビーパウダーには多くの種類がありますが、そのうちの 1 つが液体タルカムパウダーです。液体タルカム...
ハイヒールの選び方
女の子は誰でも、ある年齢に達するとハイヒールを履く必要があります。その理由の 1 つは、ハイヒールが...
回腸末端炎の症状と危険性
回腸炎は、腹部の著しい膨張や痛みを引き起こす可能性があり、腸閉塞を引き起こす可能性もあります。回腸末...
リンパ節は動きますか?
リンパ組織は人体にとって極めて重要です。身体に安全をもたらすことができます。したがって、人々はリンパ...
なぜ体中が痛くなったり、弱くなったりすることが多いのでしょうか?
多くの人は、体全体に痛みや脱力感を感じても、何が起こっているのか理解していません。実際、頭と首を長時...
脚の毛を減らす方法
脚の毛が多すぎる人は多く、肌に現れると太く重くなり、非常に醜くなります。脚の毛の増加を防ぐために、通...
皮膚がんが進行するとどうなるのでしょうか?
皮膚がんの末期には、皮膚が破れて潰瘍が形成され、皮膚の周囲が真珠のような盛り上がった縁で囲まれ、内側...
フェリチンとは何か
人体には多くの元素があり、特に血液にはさまざまな元素が一緒に組織されています。したがって、これらの元...