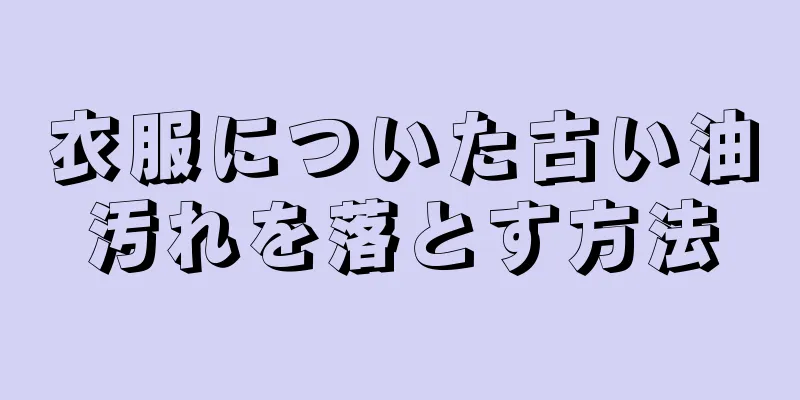CPRの3つのステップ

|
心肺蘇生法とは、緊急事態で一時的にショック状態に陥った患者に対する応急処置を指します。CPR は患者の正常な心拍を回復させ、生命を維持します。CPR では、正しい治療を行うために、要点と操作方法を習得する必要もあります。CPR の 3 つの手順は次のとおりです。まず、患者の胸を圧迫して心拍を回復させます。必要に応じて人工呼吸を行うこともできます。患者の頭を持ち上げ、圧迫の頻度に注意してください。 CPRの3つのステップは何ですか? 心肺蘇生の 3 つの基本的なステップは CAB として要約できます。 最初のステップは C: 胸骨圧迫を30回、圧迫箇所は胸骨の下部、圧迫深度は5~6cm、頻度は1分間に100~120回。気道が開いている (A):一般的には額を押さえて顎を上げる方法です。最後に、口対口人工呼吸 (B) 2回、1回につき1秒以上吹きます。吹き出す前に普通に息を吸い込みます。患者が回復するか救急隊員が到着するまで、圧迫 30 回と減圧 2 回というこのプロセスを繰り返します。 追加手順 1. 判断力 両手で患者の肩を軽くたたき、患者を呼び、反応があるかどうか観察します。 2. 助けを求める 直ちに他の医療関係者に救助を要請し、除細動器を持ってきてください。 3. 心拍と呼吸を確認する 掛け布団を持ち上げて、上着のボタンを外し、頸動脈に触れ、胸の上下動を観察して心拍と呼吸の状態を判断します。心臓が止まったり、呼吸が止まったりした場合は、すぐに心肺蘇生を行い、救助開始時間を記録してください。 4. 胸骨圧迫(C) (1)準備:ベッドサイドテーブルを移動し、圧迫板と足台を胸の下に置き、枕を使わずに患者を仰向けに寝かせます。 (2)胸骨圧迫30回(完了まで17秒) A. 位置: 剣状突起の上にある2つの乳首または2本の水平指を結ぶ線の中点 B. テクニック:手を重ね、手首と肘をまっすぐに伸ばし、体の重力を利用して垂直に下向きに押します。 C. 深さ:胸骨陥没 ≥ 5cm D. 頻度: ≥100回/分 5. 気道を開く(A) (1)気道の洗浄:患者の頭を横に向け、右手の人差し指を使って口内の異物を除去します。 (2)気道を開く:気道を開く方法としては、あごを上げて仰向けに寝たり、顎を突き出すなどの方法があります。一般的に使用されている仰向け顎上げ法は、救助者が左手の小指を患者の額に当て、手のひらを後ろに押して頭を後ろに傾ける方法です。右手の中指と人差し指をはさみの形に分け、患者の顎の下に置き、上方に持ち上げて気道をまっすぐにします。首を負傷した患者には、脊髄を傷つけないようにするために禁止されています。 6.人工呼吸(B) 簡易人工呼吸器を使用して2回換気し、「EC法」を使用し、6〜8秒ごとに1回、8〜10回/分の人工呼吸を行い、1回の呼吸は約1秒、換気は約0.5リットルで、胸の上下が確認できます。 7. 持続的心肺蘇生 胸骨圧迫と人工呼吸の比率を30:2にして心肺蘇生を継続し、回復するまでこの方法を繰り返します。 8. 心肺蘇生の有効な兆候を観察する (1)心拍と呼吸を観察する:頸動脈に触れ(10秒)、呼吸を観察します。 (2)観察認識:瞳孔の変化、眼窩圧反応、光反射を観察する。 (3)循環を観察する:顔面、唇、爪床のチアノーゼの変化、末梢循環の改善を観察し、血圧を測定する。 (4)蘇生が成功したかどうかを判断する:高度な生命維持を継続する。 9. 整理して記録する (1)圧迫板を外し、患者の衣服を整え、患者の頭の下に枕を置き、患者を掛け布団で覆い、ヘッドボードを取り付けます。 (2)手を洗い、救助の過程を記録する。 |
推薦する
腎臓の健康に最適な漢方薬は何ですか?
現代社会では、人々の生活のペースはますます速くなり、仕事のプレッシャーもますます大きくなり、多くの人...
口がピクピクする原因は何ですか?
口角がピクピク動くのは、日常生活でよく見られる現象です。大人の場合は顔面けいれん(顔面筋のピクピク)...
ダイエット中にアボカドを食べてもいいですか?
アボカドは栄養価が高いため、ダイエットの達人と言えます。体内のコレステロールを効果的に下げることがで...
電気溶接による目の痛みを和らげる方法
溶接による傷害は目の痛みを引き起こしますが、これは特に溶接時によく見られる現象です。電気溶接工は不注...
Amazonが42のFBA倉庫を閉鎖!北米の貯蔵容量は急速に減少している
最近、海外メディアは、アマゾンが米国全土のFBA倉庫を閉鎖し、一部の倉庫拡張計画をキャンセルしており...
首にしこりがあって、押すと痛いです。これが原因です。
首にしこりができると、それだけで非常に悪い連想を抱くことになります。また、押すと痛いなどの症状が伴う...
グレープフルーツ梨ジュース
グレープフルーツはザボンの一種で、グレープフルーツジュースを作るのが最も一般的な方法です。生のグレー...
メラニンを補給する果物
メラニンは人体にとって重要な分子です。メラニン含有量が少なすぎると、白い斑点が現れ、患者の肌の色が他...
心臓への血液供給不足を補うために何を食べるべきか
心臓の重要性は誰もが知っています。心臓の問題は絶対に良いことではなく、真剣に受け止めなければなりませ...
妊娠初期に胸にキスしても大丈夫ですか?
妊娠に気づく前、若いカップルの多くは非常に情熱的で、ほとんどいつも一緒にいます。このようにして、彼ら...
お腹が冷えて吐きそうなときはどうすればいいですか?
もちろん、胃腸の冷えは生活習慣や食習慣の悪さが原因の場合が多いので、胃腸の調子を整えることにも注意が...
おしゃぶりには使用期限がありますか?
ほとんどのおしゃぶりは赤ちゃんを落ち着かせることができますが、おしゃぶりを吸うことが赤ちゃんの体に影...
優生学・子育て検定の項目は何ですか?
優生学と良き子育ては我が国が提唱するものであり、新しい時代において新生児人口に提示された希望であり要...
胸部横隔膜炎の症状は何ですか?
胸膜中隔炎は結核感染によって引き起こされ、最初は隣接する臓器のみを脅かすだけですが、適切に治療しない...
オレンジの皮の枕の作り方
実は、生活の中で自分の体の変化をとても気にしている人はたくさんいますが、最近は健康維持にもっと注意を...