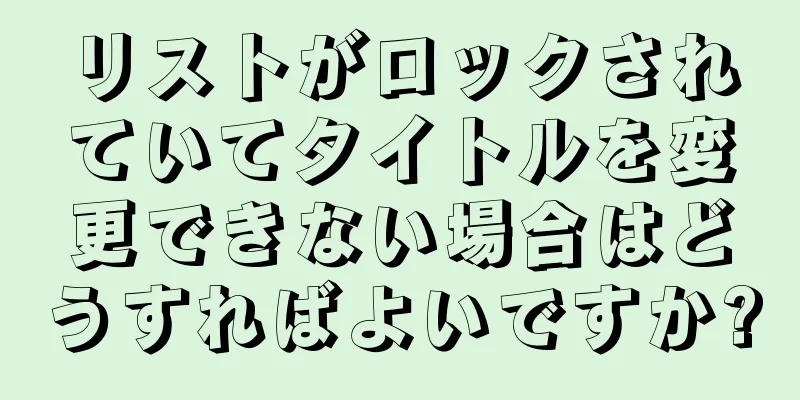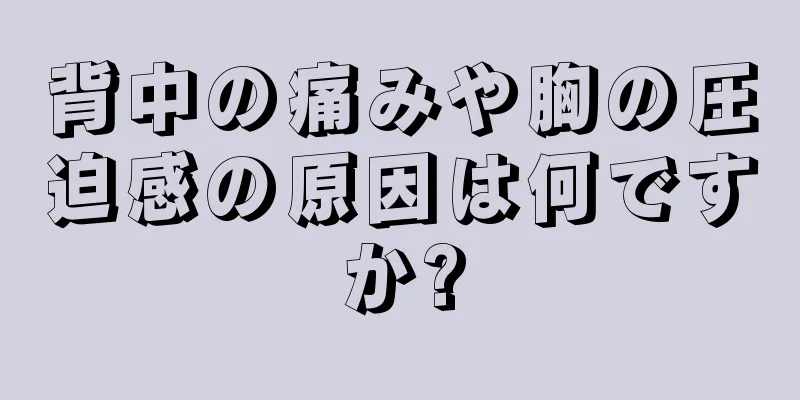環柱の働きは何ですか?

|
環柱は人体にとって非常に重要なツボです。このツボをマッサージすることで病気の治療に役立ちます。例えば、環柱をマッサージすると脾臓が強化され、気力が補充されます。また、全身に風寒湿の関節炎やリウマチ性疾患がある場合、環柱をマッサージすることで治療に役立ちます。マッサージに加えて、鍼治療も使用できます。以下は、環柱の多くの機能の詳細な紹介です。 環柱の働きは何ですか? ツボの選択方法 横向きに寝て、大腿部を曲げてツボの位置を確認し、下腿を伸ばし、上腿部を曲げてツボの位置を確認します。環柱ツボは、臀部、大腿骨大転子の最も凸状の点と仙骨管裂孔を結ぶ線の外側 1/3 と内側 2/3 の交点にあります。 生理学的解剖学 大殿筋と梨状筋の下縁、内側には下殿動脈と下殿静脈があり、下殿皮神経と下殿神経が分布し、奥には坐骨神経があります。 環柱の下には、皮膚、皮下組織、殿筋膜、大殿筋、坐骨神経、内閉鎖筋(腱)、および上部双子筋と下部双子筋があります。皮膚は、腸骨下腹神経の側枝と上殿皮神経の二重の支配を受けています。皮下筋膜はよく発達しており、繊維と脂肪組織が豊富です。臀部の後部と下部には脂肪パッドを形成する肥大した高密度の脂肪があります。坐骨神経は大殿筋の深部で、内閉鎖筋の上にある下梨状筋孔を通って骨盤から出ます。このポイントの表面は、後上棘椎と坐骨結節を結ぶ線の中間点に位置し、下方向には、坐骨結節と大腿骨大転子を結ぶ線の中間点よりわずかに内側に投影されます。坐骨神経の内側には、後大腿皮神経、下殿神経、血管、陰部神経、血管などがあります。神経の下の内閉鎖筋腱とその上下の上部および下部の筋肉はすべて、仙骨神経叢の筋枝によって神経支配されています。 階層的解剖学:皮膚 → 皮下組織 → 大殿筋 → 坐骨神経 → 大腿方形筋。 下殿皮神経と下殿神経に覆われ、深部は坐骨神経、内側は下殿動脈と下殿静脈です。 環引ツボの機能 特異性: 足の少陽経絡と太陽経絡の交差点。 環田経穴の意義:胆経の水分はここで大量に天陽エネルギーに変換されます。 気血の特徴:気血の成分は地からの水分と湿気、天からの陽です。 動作ルール:地中の水と湿気が脾臓と土に浸透し、天のエネルギーが人体のさまざまな部分に伝達されます。 機能と効果:脾臓を強化し、気を補い、風と湿気を払い、腰と膝を強化します。環柱のツボには、経絡と側副血行路を浚渫し、腰と腎臓を強化し、風と寒を払う効果があります。 注: 足の少陽経と太陽経の交わる点。 適応症 環柱経穴は主に腰、脚、下肢の病気の治療に使用されます。腰や臀部の痛み、下肢の麻痺、膝やすねの痛み、風冷やリウマチ、発疹、浮腫など。 現在、環引経穴は坐骨神経痛、下肢麻痺、股関節およびその周囲の軟部組織の炎症などの治療によく使用されています。 環柱経穴は主に、腰や脚の痛み、下肢麻痺、片麻痺、蕁麻疹、水虫、坐骨神経痛、股関節疾患などの治療に使用されます。 ·運動器疾患:坐骨神経痛、下肢麻痺、脳血管疾患後遺症、腰痛、股関節および周囲の軟部組織疾患、水虫。 その他:風邪、神経衰弱、蕁麻疹、湿疹。 |
推薦する
肺の聴診部位と順序
肺機能に問題があると感じたら、すぐに病院に行く必要があります。医師は聴診による検査を行うことがよくあ...
真菌性皮膚疾患とは何ですか?
真菌性皮膚疾患とは、真菌感染によって引き起こされる皮膚病変を指し、多くの場合、皮膚、粘膜、髪、爪など...
乳管鏡検査は痛いですか?
カテーテル検査は現在、婦人科の一般的な検査技術です。多くの女性は、身体に何らかの臨床症状を感じた後、...
腕を回すと肩から音が鳴ります。
腕を回すと肩に音がする。この問題に遭遇したことがある人は多いと思います。この問題が若い人に起こった場...
手術後の視界のぼやけ
白内障を患う多くの友人にとって、治療には一般的に手術が選択されます。しかし、白内障の手術を受けた後も...
歩くときに股関節が痛む
骨疾患は中高年層に非常に多く見られます。注意しないと股関節に痛みが生じます。股関節の痛みは通常、腰椎...
レーザー脱毛は永久に有効ですか?
夏には、きれいなスカートやサスペンダーを着るために脇毛を剃る女の子が多くいます。また、手足の毛を除去...
腎臓に栄養を与え、利尿を促す食べ物は何ですか?
現代人は仕事が忙しいため、長時間パソコンの前に座っているだけでなく、夜帰宅してからは家事や掃除もしな...
カビの生えた衣類をきれいにするにはどうすればいいですか?
雨季が多くなり、天候も南風の季節に属しているため、衣類にカビが生えやすくなります。衣類に付いた黒い斑...
スカーフの結び方
スカーフは多くの人に愛されており、特に冬には大きなスカーフを好む人が多くいます。女の子の中には男の子...
火傷の水ぶくれは自然に治りますか?
調理やお湯を沸かすときに注意しないと、火傷をします。一般的に、火傷をすると水ぶくれができます。水ぶく...
先延ばしの危険性は何ですか?
先延ばしは、先延ばしを主な症状とする先送り行動であり、他の症状を伴うこともあります。したがって、先延...
背中、脊椎、臀部に痛みがある場合はどうすればいいですか?
脊椎は人体にとって非常に重要な骨です。脊椎は上半身を支える主要な部分であるため、脊椎は人の背骨である...
ベビーブランケットの包み方
赤ちゃんが生まれたばかりのとき、それは両親と家族に大きな幸せをもたらします。この時期の赤ちゃんは特に...
縮れた髪をまっすぐにする方法
真っ直ぐな黒髪は女神の基準であり、ほとんどの女性は髪が滑らかで輝くことを望んでいます。髪が美しいと、...