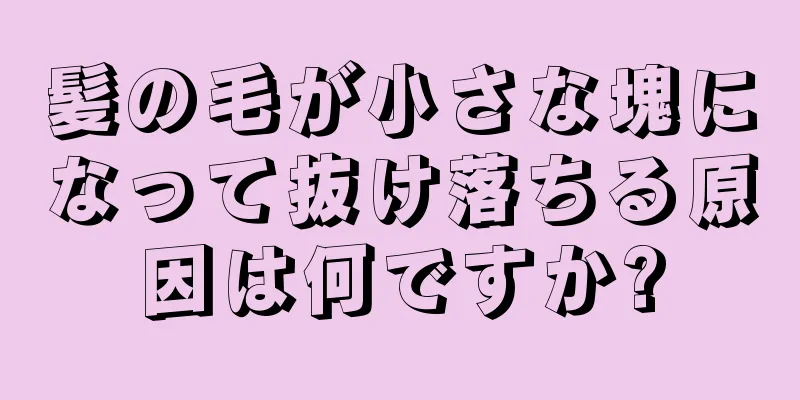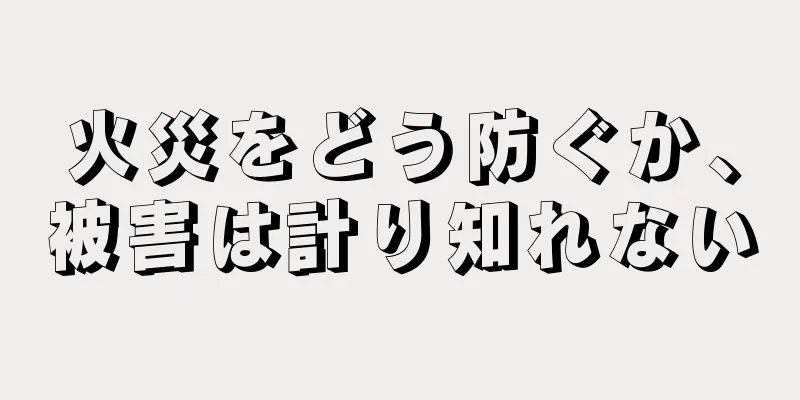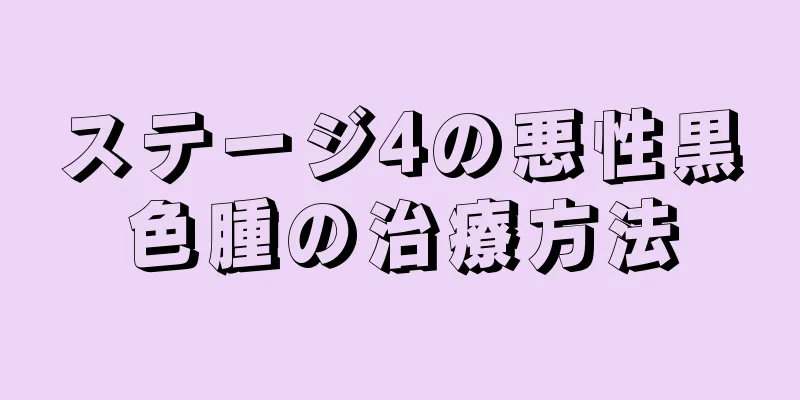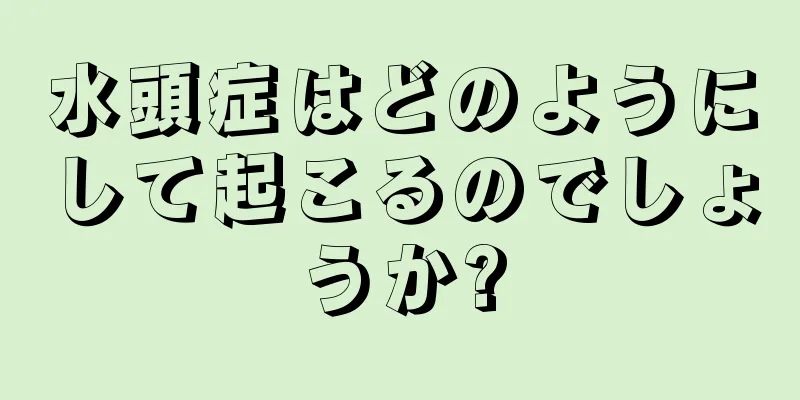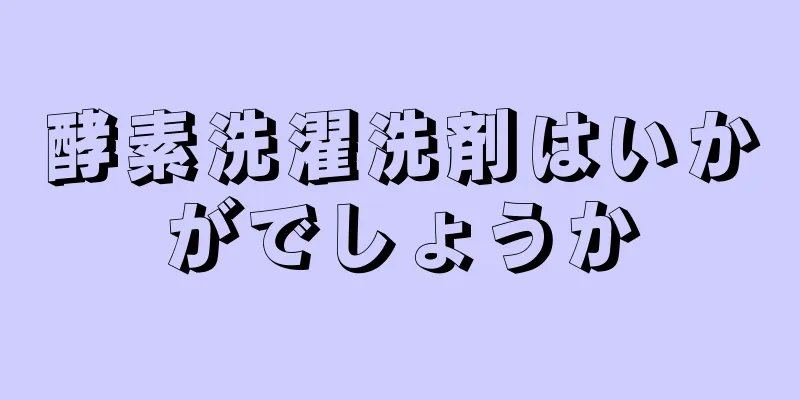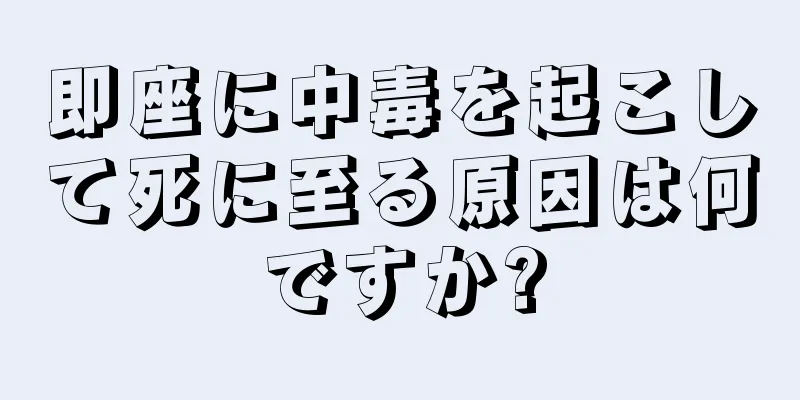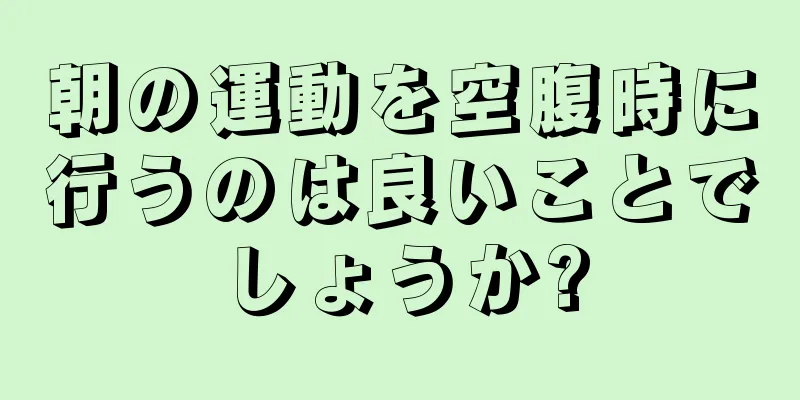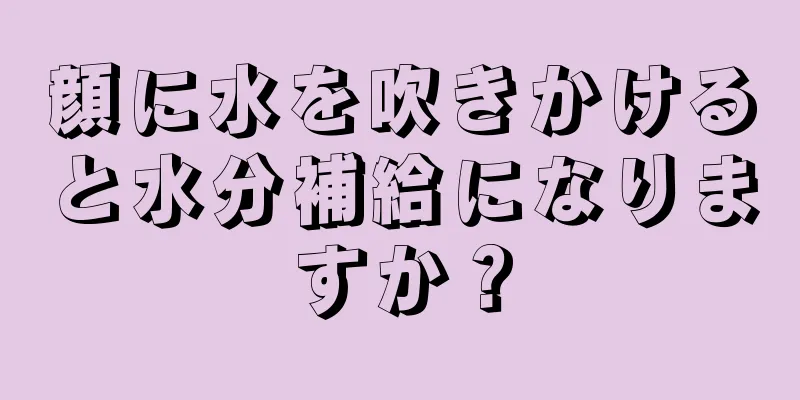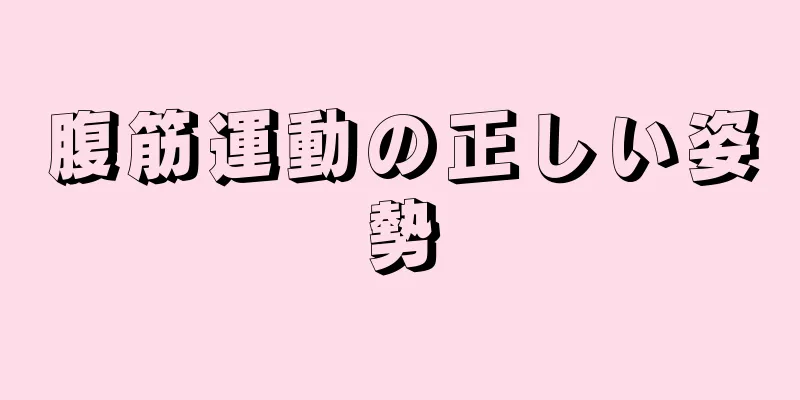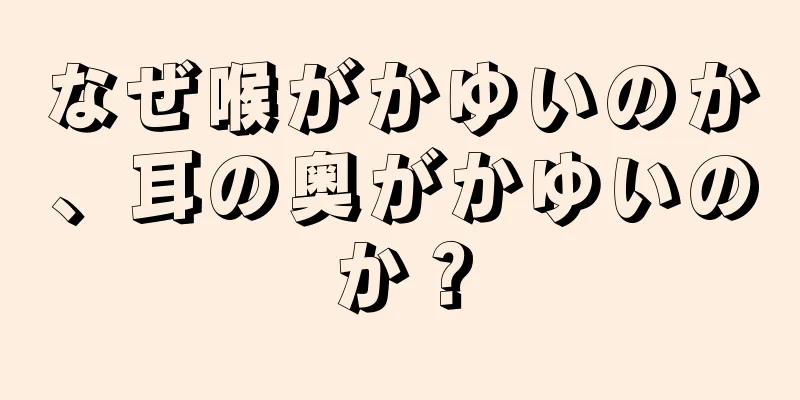夜間のしゃっくり

|
しゃっくりは、胃の中にガスが多すぎるために起こります。ガスが時間通りに体外に排出されないと、お腹が張って不快感を覚えます。ガスを排出する方法は2つあります。1つはおならをすること、もう1つはしゃっくりをすることです。どちらの方法を使っても、不快感を覚えます。しかし、排出されないと、さらに不快感が増します。では、なぜ夜にしゃっくりをするのでしょうか? 夜に脂っこいものを食べすぎたか、お腹がいっぱいだったことが原因かもしれません。しゃっくりは実は胆嚢炎によって引き起こされます。これには理由があります。胆嚢の機能が低下すると、胆汁の代謝が低下する可能性があります。胆汁の量が減ると、食べ物が胃や腸内に留まる時間が遅くなります。その結果、食べ物が胃の中に長く留まりすぎ、胃酸の分泌が以前よりも増加し、解消しにくい膨満感を引き起こします。 諺にもあるように、下から下へ降りて行かなければ、上から降りて行かなければ、しゃっくりは避けられません。夜寝る前にしゃっくりが止まらないのは、夜に食べる食べ物が脂っこいか、満腹のせいかもしれません。胆のうが悪い場合は、適当な時間に木から苦いハーブを摘んでスープを作り、黒砂糖を少し加えて苦味を消すと、苦くなくなります。生の食べ物、冷たい食べ物、脂っこい食べ物を控え、特に夜更かしをしないようにしてください。これは特に重要です。 しゃっくりは胃から空気がげっぷとして出る現象で、喉の中で頻繁かつ速く短い音が出ます。これは横隔膜のけいれんと収縮によって引き起こされる一般的な生理現象です。健康な人でも一時的なしゃっくりを経験することがありますが、これは食事、特に早食い、食べ過ぎ、非常に熱いまたは冷たい食べ物や飲み物の摂取、飲酒などに関係していることが多いです。外気温の変化や過度の喫煙もしゃっくりを引き起こすことがあります。頻繁に起こったり、24 時間以上続くしゃっくりは難治性しゃっくりと呼ばれ、特定の病気でよく起こります。 しゃっくりは横隔膜のけいれんによる収縮運動によって起こります。息を吸うと声門が突然閉じて、短い音が出ます。横隔膜の片側または両側に発生することがあります。正常で健康な人でも、飲み込むのが速すぎたり、空気を急に飲み込んだり、腹腔内圧が急激に上昇したりすることで、しゃっくりが起こることがあります。それらのほとんどは自然に消えます。しゃっくりの中には、長時間続くものもあり、持続性しゃっくりになることもあります。 発作中、胸部X線検査により、横隔膜痙攣が片側性か両側性かがわかります。必要に応じて、胸部CTスキャンを実施して横隔膜神経を刺激する疾患を除外し、心電図検査を実施して心膜炎や心筋梗塞があるかどうかを判断します。中枢神経疾患が疑われる場合は、頭部CT、MRI、脳波などの検査が行われます。 消化器系の病変が疑われる場合は、必要に応じて腹部X線検査、Bモード超音波、消化管血管造影、腹部CT、肝膵機能検査を実施します。また、中毒や代謝性疾患を除外するために臨床生化学検査を実施することもできます。 |
>>: レーザーによるそばかす除去後、どれくらいで洗顔できますか?
推薦する
消化管出血とは何ですか?
消化管出血は一般的な臨床症候群であり、一般的な十二指腸疾患や胃食道領域の病変など、消化管出血の症状を...
肺癒着の症状
肺癒着は比較的一般的な肺疾患であり、主に人の肺臓器が癒着し、正常に機能できなくなる現象を指します。重...
Amazonが公に反応!売り手の責任を分担する
今月中旬、カリフォルニア州の裁判所が、サードパーティ販売業者の製品の品質問題に関して Amazon ...
空腹時血糖値6.8は正常ですか?
健康診断を受ける場合は、正確な結果を得るために、特に血液検査のために採血を受ける場合は朝食を食べるこ...
キウイフルーツが酸っぱすぎるときの食べ方
キウイは熟していないので酸っぱすぎます。この時期のキウイは、たいていまだ比較的硬いです。このまま食べ...
胸部CTスキャンで何がわかるのでしょうか?
現代医学の継続的な発展により、身体検査のためのより便利な機器が多くあり、胸部CTは比較的一般的な検査...
キルトを太陽の下で乾かすとダニは死滅しますか?
キルトは日常生活にとても一般的で、必要不可欠です。しかし、キルトを長期間使用すると、ダニや細菌が繁殖...
解毒のために緑豆スープをどれくらい煮込むべきか
緑豆スープは栄養価が比較的高く、一定の薬効があり、タンパク質、脂肪、各種ビタミンが豊富で、熱を清めて...
秋は汗蒸しがいいのでしょうか?
蒸し風呂は健康維持にとても人気のある方法です。蒸し風呂に入ると、人体の皮膚の毛穴が広がり、血液の循環...
神経痛をチェックする最良の方法は何ですか?
頭痛は非常に厄介な症状です。この症状の発生は人々の生活に大きな影響を与え、患者の生活を非常に苦痛にし...
オーバーナイトミルクを飲んでも大丈夫ですか?
牛乳はカルシウムとタンパク質を多く含む乳製品の一種であることは誰もが知っています。牛乳の栄養価はかな...
O脚に似合う服装とは
女性の友人のほとんどが、このことわざを聞いたことがあると思います。「世の中に醜い女性はいない。いるの...
目が乾燥して痛い場合はどうすればいいですか?
目の乾燥や腫れは日常生活で非常によく見られます。患者の身体の健康に大きな害を及ぼすだけでなく、通常の...
ふくらはぎに筋肉がついてしまったらどうすればいいでしょうか?
ふくらはぎの筋肉は、特に女性にとって、足全体の形に影響を与えます。このとき、筋肉をリラックスさせ、局...
片麻痺が何を意味するかご存知ですか?
片麻痺は高血圧、脳卒中、心血管疾患、脳血管疾患などによって引き起こされる運動障害です。片麻痺の患者は...