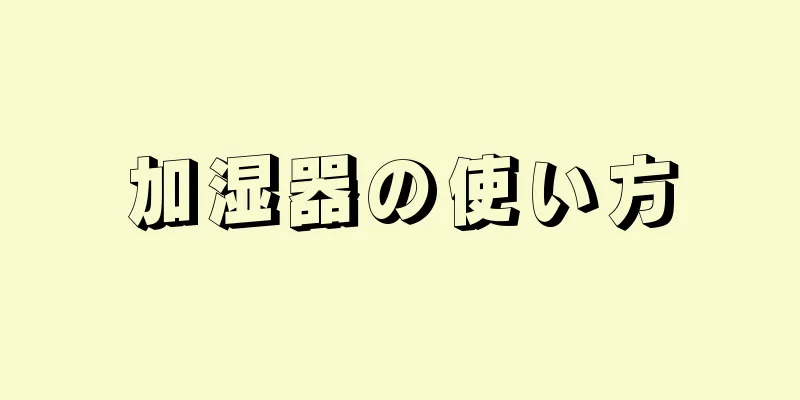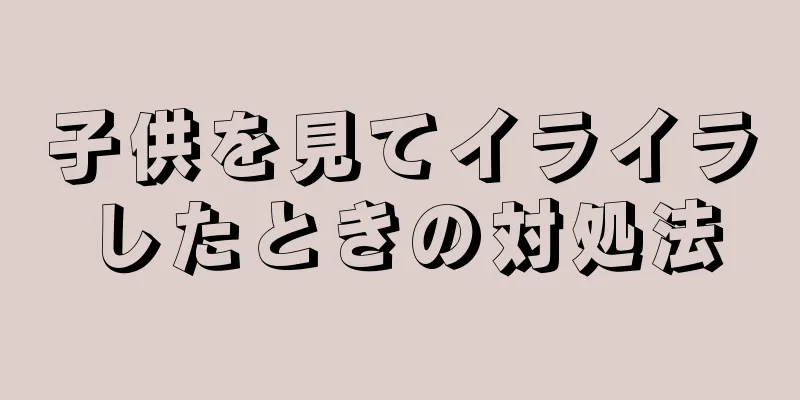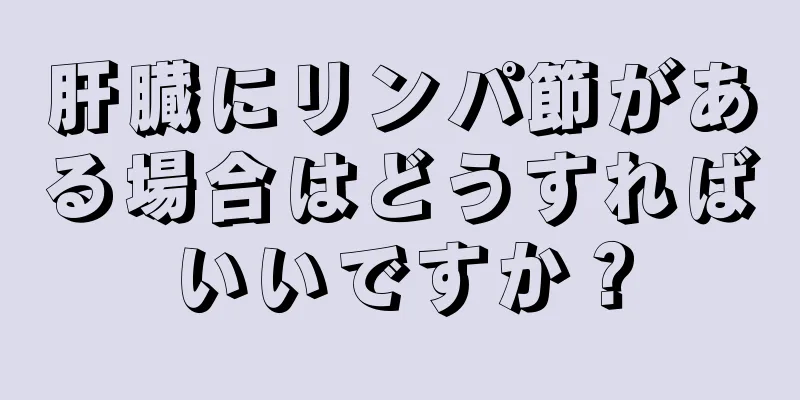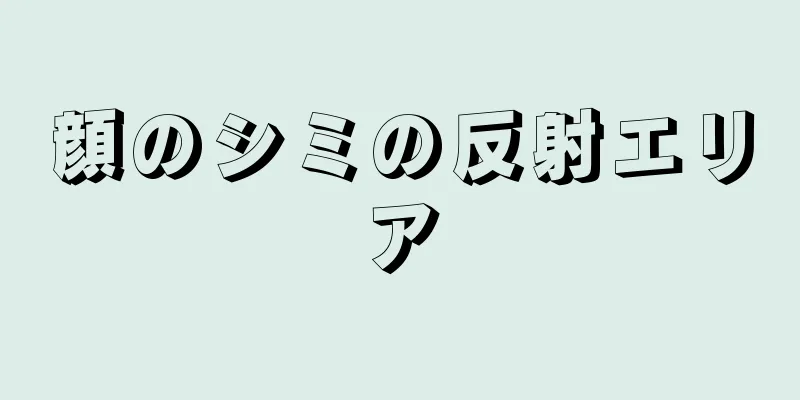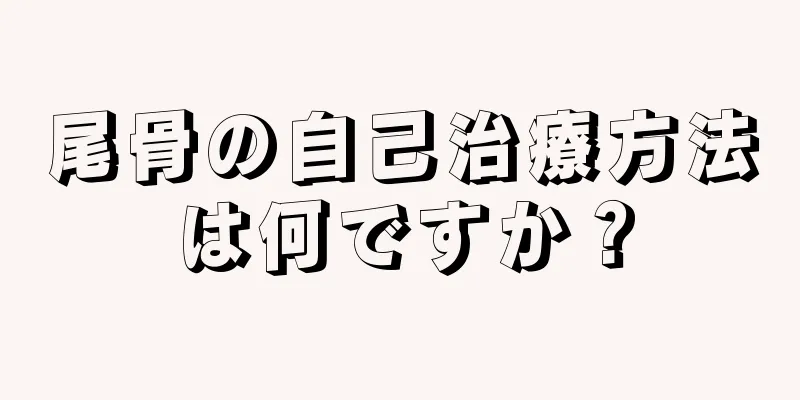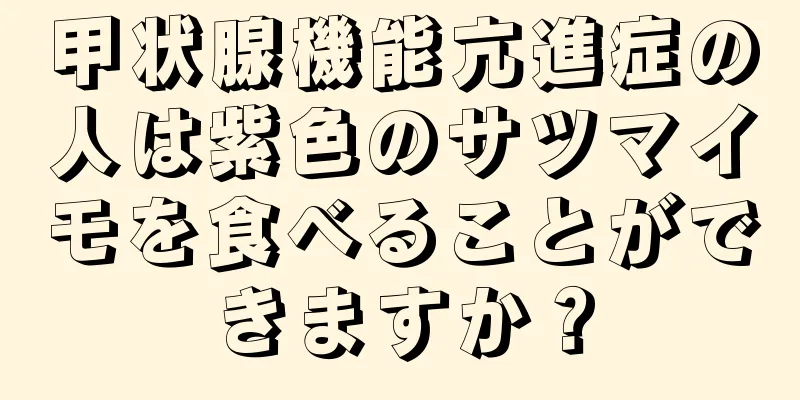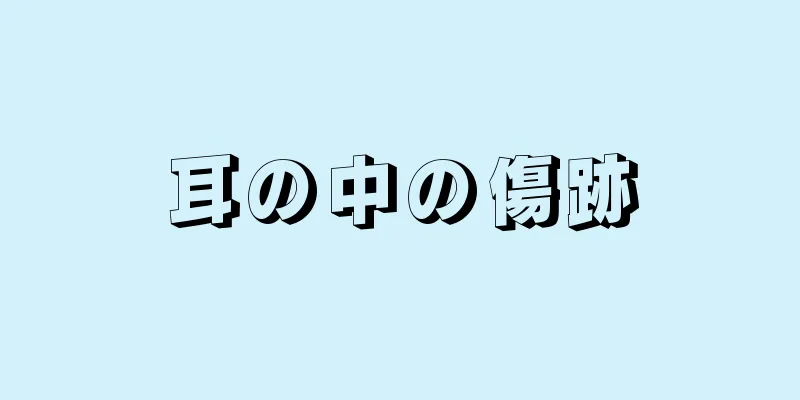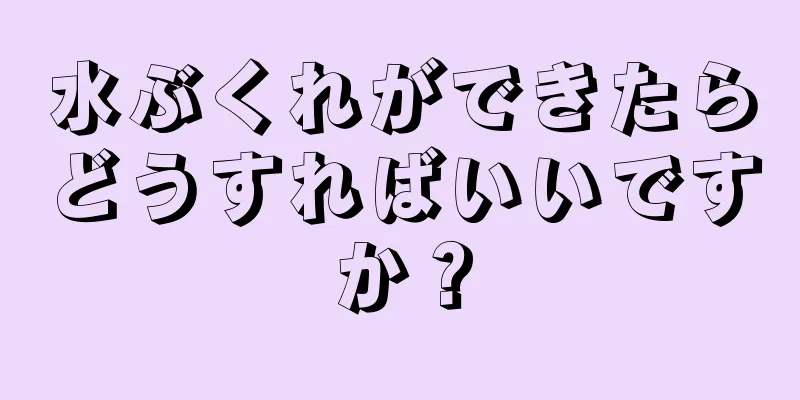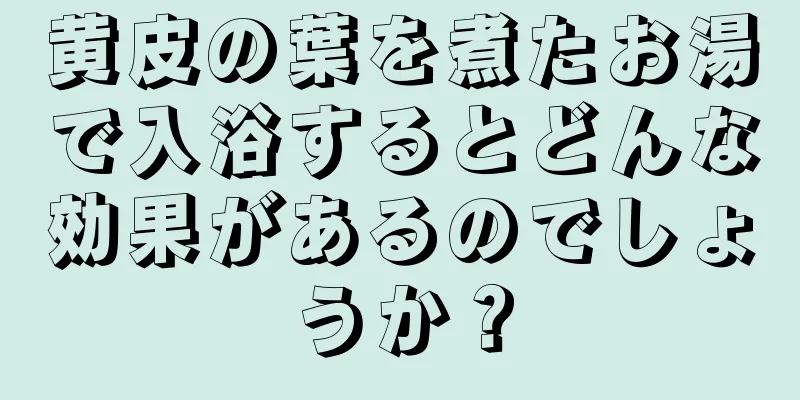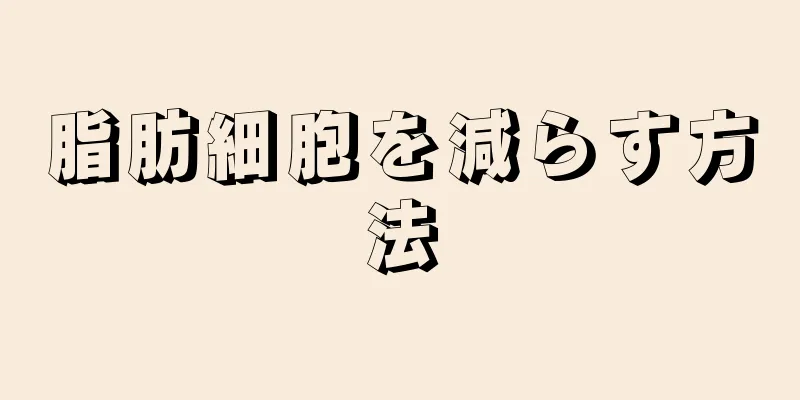B超音波検査は頻繁に行ってもよいですか?
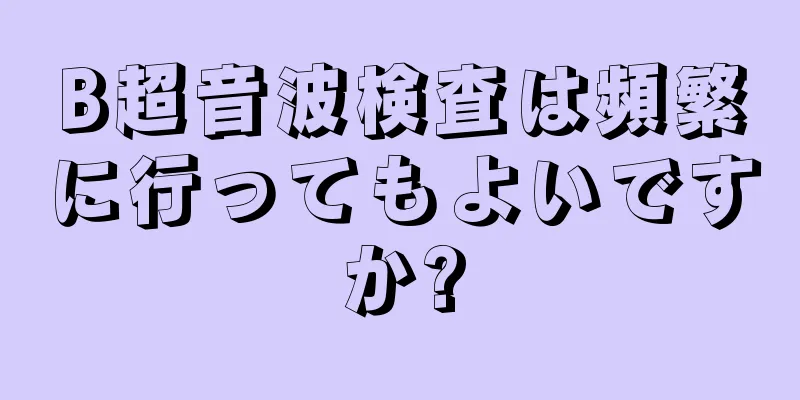
|
医療技術の発展に伴い、臨床的に身体を検査する方法は数多くあります。B-超音波はよく知られており、非常に伝統的な検査方法でもあります。近年、現在の3次元カラー超音波など、B-超音波には多くの開発がありました。この検査方法はより高価ですが、検査結果はより明確です。B-超音波検査を行うときは、誰もが関連事項に注意する必要があります。B-超音波は頻繁に行うことができますか? B超音波検査は頻繁に行ってもよいですか? 妊娠したら、妊娠しているかどうかを確認するために、大きな病院で超音波検査を受けることを選びます。この方法だと検査の精度も上がり、女性も安心できます。初めて妊娠する母親は、胎児の発育状況を定期的に知りたいので、超音波検査を受けたいと思うでしょう。妊娠中に頻繁に超音波検査を受けることはできますか? 妊娠中にB超音波検査を頻繁に受けても大丈夫ですか? 妊娠中は、胎児の状態を把握するために、毎月超音波検査を受ける必要があります。お腹に痛みや不快感がある場合は、病院で検査を受ける必要があります。超音波は一般的に胎児に害を及ぼさないので、妊婦は心配する必要はありません。 妊娠中にB超音波を頻繁に行っても、一般的に害はありませんが、カラー超音波、特に4次元カラー超音波は放射線量が高く胎児に大きな害を及ぼす可能性があるため、頻繁に行わない方がよいでしょう。そのため、女性の友人は注意を払い、胎児の心拍数を適切に聞く必要があります。 妊娠中に気をつけるべきこと 妊娠中、妊婦は良い生活習慣を維持し、規則正しい生活を送り、早寝早起きをし、喫煙場所を避ける必要があります。特に、個人の衛生に気を配り、毎日昼寝をしてください。妊婦は疲れやすいので、昼休みにゆっくり休むのも良いでしょう。同時に、幸せな気分を維持することに注意し、極端な喜びや悲しみを避けてください。 実際、妊婦に何らかの影響を与えるものはたくさんあります。まず第一に、胎児の発育と成長を脅かすことになります。胎児が子宮内でより良く成長できるようにするために、妊婦は頻繁に検診を受けるべきではありません。これは胎児に特に大きな影響と害を与えるからです。分からない場合は医師に相談すれば、詳しい計画と時間を教えてくれます。 |
<<: 出産後、夫が性欲を示さなくなったらどうすればいいでしょうか?
推薦する
お粥が溢れずに炊ける炊飯器はどれですか?
炊飯器は炊飯だけでなく、お粥を作ることもできます。しかし、炊飯器の主な機能は炊飯であるため、お粥を作...
近視用メガネを正しくかける方法
近視の人が増え、メガネをかける人も増えています。すでに近視であるにもかかわらず、近視がさらに進むのを...
チャイブとネギの違い
チャイブとニラはどちらもよく食べる野菜ですが、多くの人がこの2つを混同しがちです。同じ野菜だと思って...
ポンプボトルの開け方
私たちの日常生活で使うものの多くはプレスボトルです。プレスボトルにはさまざまな素材があり、使い勝手が...
37歳の正常な心拍数
諺にもあるように、男性は31歳で最盛期、女性は30歳で老けます。37歳になると、すでに30歳を過ぎて...
関節液貯留とは
関節液貯留とは、関節腔内に液体が溜まることを指し、比較的よく見られる健康問題です。関節液貯留が発生し...
激しい運動は有益でしょうか?
重度の湿疹の人は漢方薬で症状が改善することが多いのですが、重度の湿疹の人には運動が効果的かどうかを知...
膝へのオゾン注入の副作用
昨今、高齢者は皆リウマチ性疾患を患っており、膝の痛みは高齢者の間で非常に一般的です。膝の痛みは日常生...
カルシウム不足の場合に食べるべき食品
思春期の子供は二次的な身体的特徴に加えて、身長も急速に伸びるので、親はカルシウム不足による足の痛みを...
Amazonは本当に解体されてしまう!米国の独占禁止法調査結果が発表される
我々は以前、米国の関連反トラスト当局によるアマゾンに対するいくつかの調査について報告したことがある。...
脳梗塞の患者さんは何を食べるべきでしょうか?
脳梗塞患者の治療では、日常の投薬に加え、看護も非常に重要な部分です。多くの面で制限があり、そうしない...
もやもや病の症状は何ですか?
もやもや病についてはあまり知られていません。これは比較的まれな脳血管疾患で、脳の両側の動脈輪が狭窄ま...
副交感神経はどのようにして筋肉を制御するのでしょうか?
副交感神経系は私たちの体にとって非常に重要です。例えば、私たちの体のストレス反応は副交感神経系を通じ...
食欲を刺激しない抗炎症薬
抗炎症薬の主な機能は、傷の回復を助け、細菌を効果的に殺し、感染の問題を回避することです。抗炎症薬のこ...