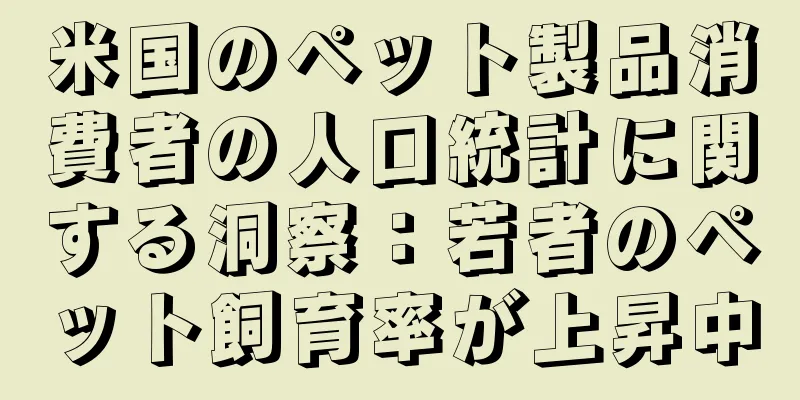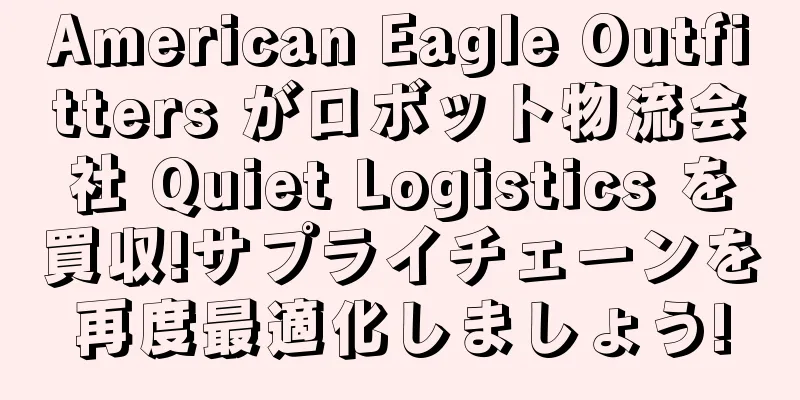肛門粘液の原因は何ですか?

|
毎日の排便を軽視しないでください。通常の排便は努力を必要とせず、毎日時間通りに行われます。これは、胃や他の臓器が健康であり、排便時に肛門に不快感を感じないことを意味します。しかし、正常に排便できない場合、例えば便秘により肛門に激しい痛みが生じたり、さらには血や粘液が流れ出たりする場合は、深刻に受け止める必要があります。では、肛門に粘液が出る原因は何でしょうか? 肛門粘液分泌の原因は何ですか? 肛門周囲膿瘍、痔、大腸炎、直腸病変、括約筋弛緩、肛門変形などにより肛門瘻となり、肛門が湿潤し分泌物が出ます。 高タンパクで脂っこい食べ物は食べず、平常心で前向きな姿勢を保ち、毎日排便後と朝晩に肛門を洗浄して清潔に保ち、必要に応じてペーパータオルで肛門を保護してください。 肛門機能エクササイズ: 1. 患者は肛門を 5 秒間収縮させ、次に 5 秒間緩め、この動作を 1 日 1 回 5 分間続けます。 2. 意識的に肛門エクササイズを心を使って行います。肛門を上向きに持ち上げます。1日1~2回、1回につき30回行います。 3. 肛門収縮運動。排便前、排便中、排便後に約5分間肛門括約筋を積極的に収縮・弛緩させることで、局所の血液循環が改善され、肛門括約筋の機能が向上します。 4. 肛門拡張エクササイズ。右手の人差し指で少量の潤滑痔軟膏または抗生物質軟膏を塗り、最初に肛門を1〜2分間マッサージしてから、ゆっくりと肛門に挿入し、通常は2つの指関節の深さまで挿入し、肛門管を前、左、後ろの4方向に約3分間拡張します。人差し指を引き抜いた後、肛門に非常に少量の痔軟膏を塗り、1日1回、半月〜1か月持続します。上記は、肛門から粘液が排出される原因の紹介です。これを理解した後、この現象には多くの原因があることがわかりますので、日常生活で盲目的に薬を服用せず、良い生活習慣を維持する必要があります。まず、肛門の衛生を確保する必要があります。また、長時間座っていることを避け、仕事と休息を適切に組み合わせることができます。体に異常がある場合は、すぐに医師に相談してください。 |
推薦する
FBAは倉庫保管を停止します!物流価格が4倍に!あなたはまだこのようなアマゾンをやるでしょうか?
昨日の午後、アマゾンの担当者が突然緊急発表をしました。 3月17日から4月5日まで、 FBA倉庫保管...
乾いた咳、痰が出ない、喉のかゆみの原因は何ですか?
乾いた咳は乾いた咳であり、一般的な臨床症状です。痰や喉のかゆみのない乾いた咳の原因について、多くの人...
塩水にはどのくらいの塩が適していますか?
水は人間の生存の基盤です。1日に8杯の水を飲むことは、体に非常に有益です。実際、薄い塩水を飲むことも...
麻薬の5つの特効薬は何ですか?
麻酔薬も臨床現場でよく使用されています。麻酔薬には多くの種類があり、その用途に注意を払うだけでなく、...
親知らずの危険性は何ですか?
多くの人が親知らずが生えてきた経験があるでしょう。歯の病気を経験した人だけが、健康な歯を持つことがい...
なぜ夜になると不安や不快感を感じるのでしょうか?
夜にぐっすり眠れるかどうかは、翌日の精神状態に関係します。十分な睡眠は誰にとっても重要ですが、誰もが...
衣服についた血液の汚れを落とす方法
服装は人を作ります。清潔できちんとした服装は、他人に良い第一印象を与えます。しかし、人生にはさまざま...
米国のホリデーショッピングリズムを予測!売主広告プランも手配可能
今年、米国は初の真の「パンデミック後」のホリデーシーズンを迎えることになる。デジタルマーケティングエ...
Amazon 広告のケーススタディ (パート 2)
背景:クリスマスが近づき、2020年のピークシーズンも終わりました。過去の経験からすると、23日から...
水虫の治療に効果的なものは何ですか?
日常生活の中には、取るに足らないように見えるものでも、非常に重要な役割を果たしているものがあります。...
日本酒には賞味期限がありますか?
私たちの生活の中で、お酒を飲むのが好きな人はたくさんいます。中には、全国各地の有名なワインを飲むため...
Amazon やその他のプラットフォームで販売された乾燥機 13,000 台がリコールされました。火災の危険
米国消費者製品安全委員会(CPSC)が最近、火災の危険性があるため、 OdorStopが販売した靴・...
腕立て伏せができない場合の対処法
腕立て伏せは現在、男女ともに行える人気のエクササイズですが、一般的には男性の友人が中心です。しかし、...
痔瘻を切った後、傷は治りますか?
痔瘻はよくある病気です。痔瘻に苦しむと患者は苦しくなります。患者の日常生活、身体の健康、仕事に大きな...
デンタルフロスとは
人生には理解できないことがたくさんあります。さまざまなものはさまざまな効果をもたらすため、さまざまな...