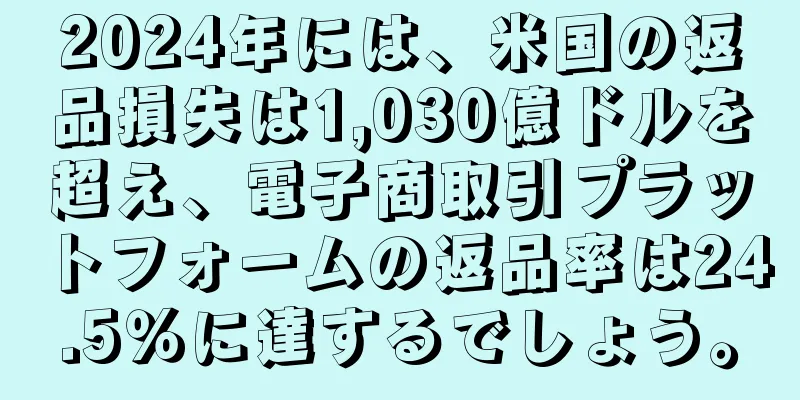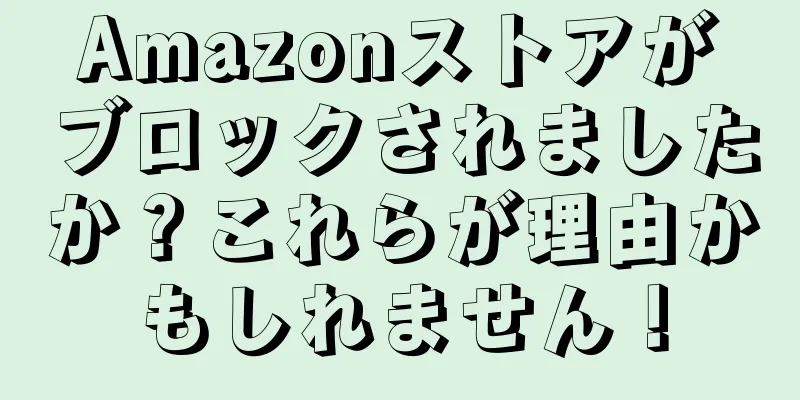エボディア・ルタエカルパの足マッサージは不眠症を治すことができますか?

|
エボディア・ルタエカルパも漢方薬の一種です。不眠症は現代人が抱える問題であり、不眠症を治療する方法は数多くあります。多くの人が、エボディア・ルタエカルパが不眠症を治せるかどうか心配しています。一般的に、エボディア・ルタエカルパに足を浸すと不眠症が緩和され、薬としても使えます。 1. 足の裏にパウダーを塗って不眠症を治す 適量のEvodia rutaecarpaを購入し、1回につき9グラムを服用し、細かく粉砕し、米酢と混ぜてペースト状にし、両足のYongquan経穴に塗り、ガーゼで覆い、粘着テープで固定します。1回につき1回塗布すると、不眠症の治療に非常に効果的です。 エボディア・ルタエカルパを3グラム取り(ヨーグルトを食べるときのように、先のとがったスプーン1杯分を使用)、上質の酢と混ぜてペースト状にします。 2つに分けて足の裏(龍泉ツボ)に貼り、粘着テープで固定します。 3日ごとに包帯を交換してください。足が冷えるのは、気血が下へ流れないからです。脾胃を養って気血を強化すると同時に、経絡を開いて気血が下へ流れるようにする必要があります。この本の中で、鍾離は「気血を下方に導く」ための3段階の方法、つまり腹部に圧力をかける、膝をつく、片足で立つ、を紹介しています。 2. 不眠症の治療には、エボディア・ルタエカルパを煮たお湯に足を浸す エボディア・ルタエカルパ40gと米酢(白酢)適量。エボディア・ルタエカルパを煎じ、ぬるま湯を加え、米酢を加え、毎晩寝る前に1回、足を足湯に30分間浸します。 3. 不眠症に効くエボディア・ルタエカルパ枕 エボディア・ルタエカルパを布で包み、枕の横に置いたり、寝るときに枕として使ったりします(枕の上に薄く敷きます)。香りを嗅ぐだけで眠くなるので、不眠症の治療にとても効果的です。薬用粉砕機を使用してエボディア・ルタエカルパ(粉砕)を加工する際、加工者がエボディア・ルタエカルパの香りを嗅ぐと、非常に眠くなることが分かりました。その時初めて、彼らはエボディア・ルタエカルパに催眠効果があることを知りました。 4. 黄耆は辛味と苦味があり、熱性があり、冷えを解消します。主に肝経に入り、肝経の寒邪を解消するとともに肝気の停滞を解消します。肝寒と気滞によるさまざまな痛みを治療する主な薬です。生姜、高麗人参などと合わせて厥陰頭痛、乾いた嘔吐と流涎、舌苔が白く、脈が遅いなどの症状によく用いられ、例えば『熱病論』の芎蓉湯のように。ウイキョウ、川芎子、茯苓などと合わせて寒邪による腹痛によく用いられ、例えば『道芎湯』(薬方箋鑑易)のように。桂枝、当帰、川芎などと合わせて充血や瘀血による月経困難症によく用いられ、例えば『文静湯』(金瓶梅)のように。パパイヤ、シソの葉、ビンロウの実などと合わせて寒湿性水虫による腫れや痛み、あるいは腹中に逆上する症状に用いる、例えば『鶏鳴末』のように。 |
<<: 塩袋温湿布は腱鞘炎の治療に効果的で、漢方薬による治療効果は良好である。
推薦する
秋に栗を食べるとどんな効果があるのか
これからの秋には栗も徐々に実り、大量に出回るようになります。栗は栄養価が高く、1日1~2個食べると栄...
Amazonはこの商品の販売を禁止しました!何千ものリストが偽物に変わりました!
▶国境を越えたナビゲーションをフォローするビデオアカウント春節休暇が終わり、各越境企業が相次いで業...
歯痛を和らげるために何を食べたらいいでしょうか?痛みを素早く和らげるためにこれを食べましょう!
歯痛は日常生活でよくある問題です。一般的には、虫歯や炎症により歯茎が腫れて痛むことが原因です。歯痛は...
ベゾスが訴訟に巻き込まれ、Amazon のこの機能は停止されました。
クロスボーダービジネススクール情報とスキルがこれほど近づいたことはかつてないほど焦点を当てる Ama...
鶏の睾丸とは何ですか?
鶏肉は人々の日常生活で非常に一般的な食べ物であり、非常に人気があります。鶏肉が美味しいだけでなく、人...
Etsy が販売者向けの支払いレポートを更新しました! 2022年の売上アップにご協力ください!
<span data-shimo-docs="[[20,"获悉,据外媒报道,近日Et...
痛風患者は牛乳を飲んでもよいですか?
痛風患者は通常、食事に多くの禁忌があります。食べられない食品が多く、特にプリン体の多い食品があります...
足の爪が厚くなる原因は何ですか?
夏は天気が比較的暑いので、足が露出するため、多くの人が足にもっと注意を払います。この時期には、足の爪...
Amazon Vine に大きな朗報があります!製品の複数のノードが厳密に検査されました
過去2日間、Amazonは裏でVineプランの新たな変更を発表し、 Vine登録半額イベントを開始し...
雲南省特産のドライフルーツは何ですか?
雲南省は非常に特殊な地域です。雲貴高原の障壁により、雲南省の気候は非常に温暖です。そのため、雲南省で...
黒砂糖にはエストロゲンが含まれていますか?
黒砂糖は日常生活で非常に一般的なもので、用途も多岐にわたります。黒砂糖を定期的に飲むことも、人間の健...
睡眠中に夢を見る場合の対処法
睡眠中に夢を見るのは実は非常に正常な現象です。しかし、頻繁に夢を見る場合、睡眠の質に影響が出ることに...
かかとの後ろの痛みの原因
体内のすべての器官は非常に重要であり、手がなければ働けず、足がなければ歩けないのと同じように、器官の...
ベーキングトレイで焼くことができる材料は何ですか
自宅でバーベキューをしたいと思っている人は多いでしょう。バーベキューの道具に加えて、食材を準備するこ...
より健康を保つにはどうすればいいでしょうか?
誰であっても、身体の健康には気を配る必要があります。よりよい健康を維持したいなら、良い生活習慣を身に...