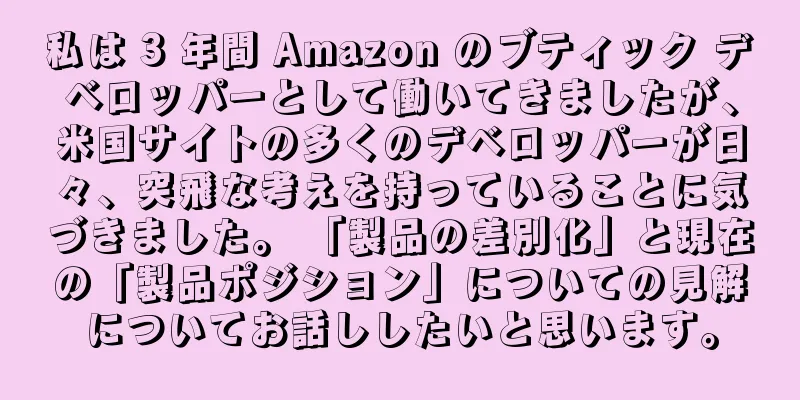米のとぎ水の成分は何ですか?

|
米のとぎ汁とは、米を洗った後に残る水です。多くの人は、米のとぎ汁がどれほど役立つかを知らずに、米を洗った後の水をそのまま捨てています。そのため、米のとぎ汁の成分を理解し、十分に活用する必要があります。次に、米のとぎ汁の成分について学び、より多くの人々が米のとぎ汁の価値を知り、もちろんよりよく活用できるようにしましょう。 米とぎ汁は米を洗うときに使う水です。この水はアルカリ性で、稲の皮の栄養分を洗い流すので、植物の水やりに効果的です。また、米のとぎ汁に含まれる水分子は、油汚れを分解し、食器をきれいにし、まな板の臭いを取り除き、包丁のサビを洗い流す効果もあります。炊事の時に米のとぎ汁を捨ててしまう人は多いですが、米のとぎ汁は役に立たないと思っている人が多いです。実は、日常生活の中で、米のとぎ汁は「多役」をこなせる天然洗剤であるだけでなく、優れた薬効も持っています。 シミ抜き 1. 米のとぎ汁を使って食器を洗うと、汚れを落とす効果が強いだけでなく、有害な化学物質が含まれていないため、洗剤よりも優れています。 2. 米のとぎ汁にはバイオアルカリが含まれており、優れた洗剤です。米のとぎ汁を使ってドアや窓、ホーロー製品、竹や木製の家具などをこすると、掃除が簡単になるだけでなく、汚染もありません。 3. 米のとぎ汁を使って痰壺を洗い、汚れを落とします。新しく塗装した家具やアイテムを米ぬかで拭くと、塗料の臭いが消え、色が鮮やかになります。 ランドリー 1. 米ぬか水は淡い色の衣類を洗うときに使います。洗浄力が強く、衣類を明るく清潔に保つことができます。汗染みのついた衣類は、洗濯する前に米のとぎ汁に浸しておくと、汚れが落ちやすくなります。カビ汚れのついた衣類を米のとぎ汁に一晩浸し、その後いつも通り洗濯すると衣類についたカビ汚れが取れます。 2. タオルに果汁や汗などが付着すると、臭いがついたり、硬くなったりします。米のとぎ汁に浸して10分以上蒸すと白く柔らかくなります。 シャンプー 米ぬか水にはビタミンBが豊富に含まれており、髪の色素細胞がメラニンを生成するのを助けるので、髪の色を濃くするのに役立ちます。 豚の腸と胃を洗う 1. 豚の腸や胃を洗うのに米のとぎ汁を使うと、塩やミョウバンでこするよりも時間が節約でき、清潔になります。 2. 市場で買った肉はホコリや汚れが付着している場合があり、水道水では洗いにくいですが、お米の熱いお湯で2回洗うと汚れが簡単に落ちます。 錆除去 包丁やフライ返し、鉄スプーンなどの鉄製の調理器具は、比較的濃い米のとぎ汁に浸けることで錆びるのを防ぐことができます。錆びてしまった場合は、まず数時間水に浸しておくと、錆びの汚れが簡単に拭き取れます。 こうしてみると、私たちの生活の中には、実は役に立つものがたくさんあることがわかります。ゴミを宝物に変えて、有効活用してみませんか?これは価値を生み出すだけでなく、物事の本当の意味を実現します。米のとぎ水の成分は、私たち一人ひとりが知っておくべきものであり、必要なときに簡単に使用できます。 |
推薦する
二重まぶたの圧迫とは何ですか?
二重まぶた手術を受けたことがある人は、プレスライン二重まぶた手術の概念と手術の一般的な方法を知ってい...
ウォルマートがSymboticとの提携を拡大! Symboticの過半数株式の62.2%を保有すると発表しました。
<span data-shimo-docs="[[20,"获悉,沃尔玛上个月扩大了与...
サツマイモ粉は食べられますか?サツマイモ麺の食べ方
サツマイモ麺は当然食べられますが、生活の中では、サツマイモ麺を使ってさまざまなおいしい食べ物を作り、...
胃酸があるときにトウモロコシ粥を食べても大丈夫ですか?
トウモロコシ粥は多くの人が朝食に選ぶ食べ物です。人体の健康に非常に有益ですが、胃酸過多の人がトウモロ...
「昆虫クリーム」など10の「未来の食品」
人間は常に無限の想像力に満ちており、その想像力を実現することが人類の進歩を推進する原動力です。食べ物...
震える声で緊張して話す
一般的に、話すときに震える人は、ほとんどが内向的な人です。彼らは劣等感があり、心に自信がないため、通...
赤汗野菜の効能と機能
実際、野菜市場で赤スッポン野菜を見かけることはほとんどありません。これは、赤汗菜が山菜だからです。赤...
小さな肉粒が成長する理由は何ですか
首は身体の中でも敏感な部分であり、長時間外気にさらされることによってトラブルが起きやすい部分でもあり...
氷枕の危険性
夏は暑すぎるので、誰もが涼しくなろうと全力を尽くします。多くの人が寝るときに氷枕を使っていますが、こ...
太ももが太くてふくらはぎが細い場合、どのように服を着ればよいでしょうか?
ほとんどの人は完璧ではありません。人生の中で、太ももが太く、ふくらはぎが細い人がたくさんいます。その...
妊娠線が現れるまでにどれくらいかかりますか?
妊娠線といえば、妊娠したことがある女性なら誰もが経験したことがある状況でしょう。妊娠線は、女性が妊娠...
リンパ節が腫れる原因は何ですか?
首の上にはリンパ系があります。リンパ節が腫れている場合は、リンパ系の病気であるに違いありません。では...
皮膚萎縮はどのように治療すればよいのでしょうか?
皮膚萎縮は、内分泌障害につながる長期の心理的ストレスなど、皮膚の栄養吸収障害に関係していることが多い...
顔面白板症は伝染しますか?
顔に白い斑点が現れる原因は、白斑である可能性があり、外見に比較的大きな影響を与えます。白斑の学名は白...
咽頭炎は食事中に詰まりを引き起こしますか?
咽頭炎を経験した人なら誰でも、喉が詰まったような感覚を経験したことがあるでしょう。話すこともできず、...