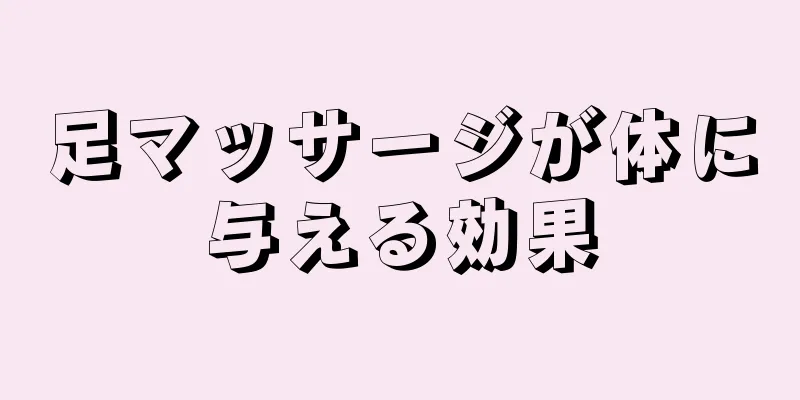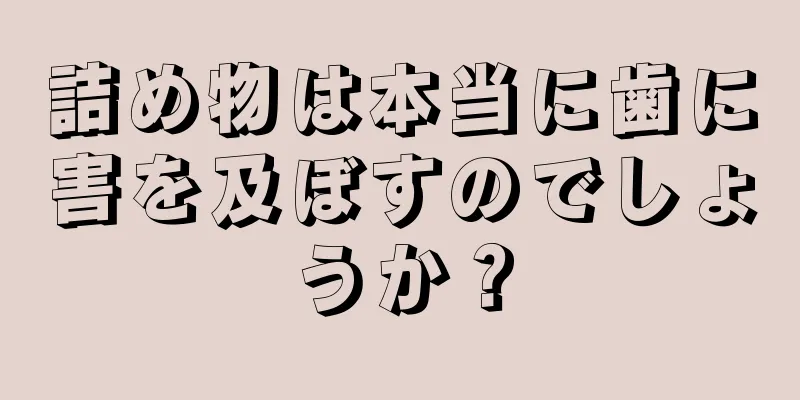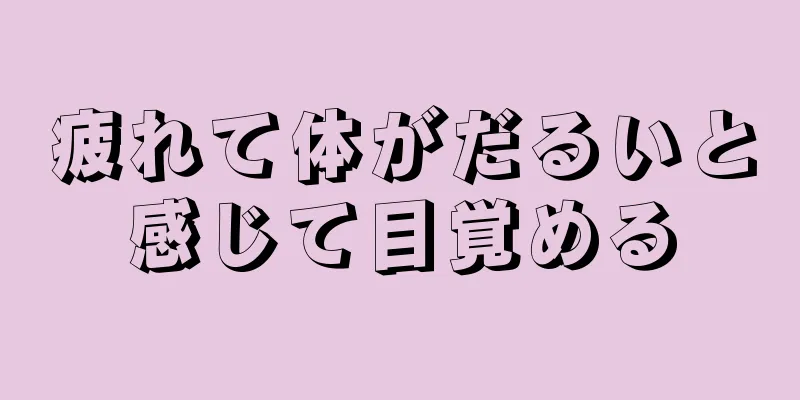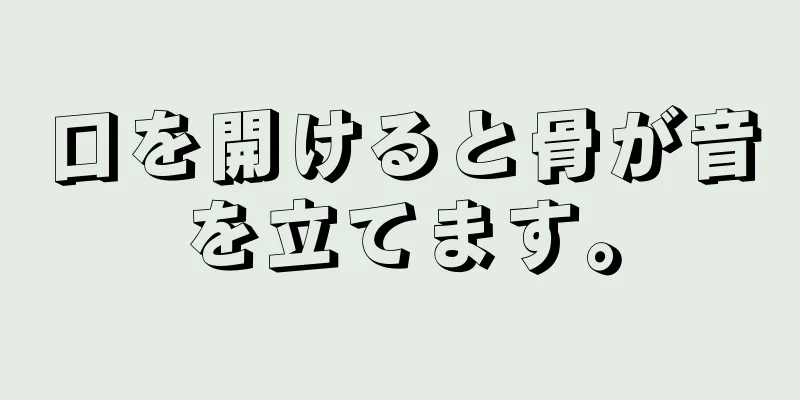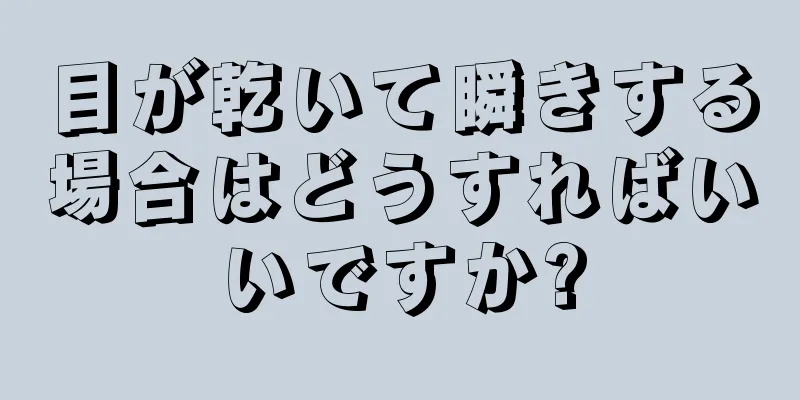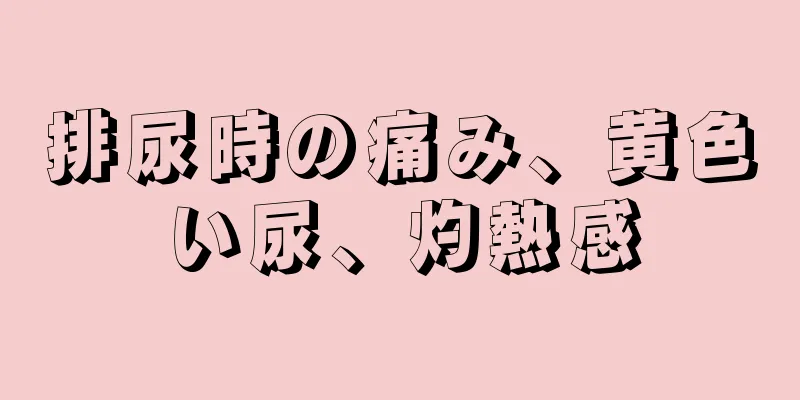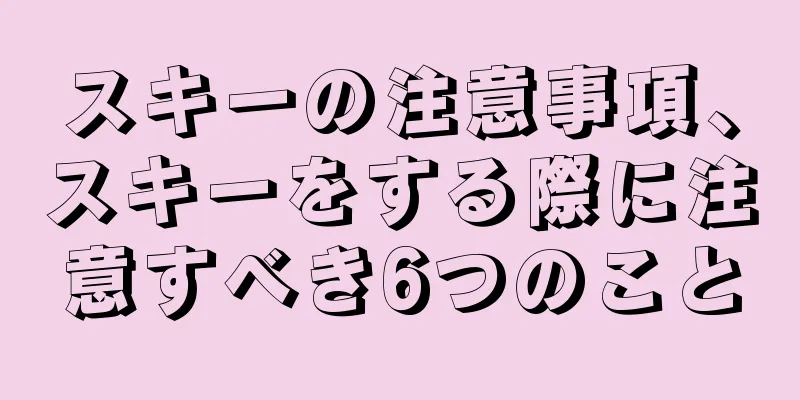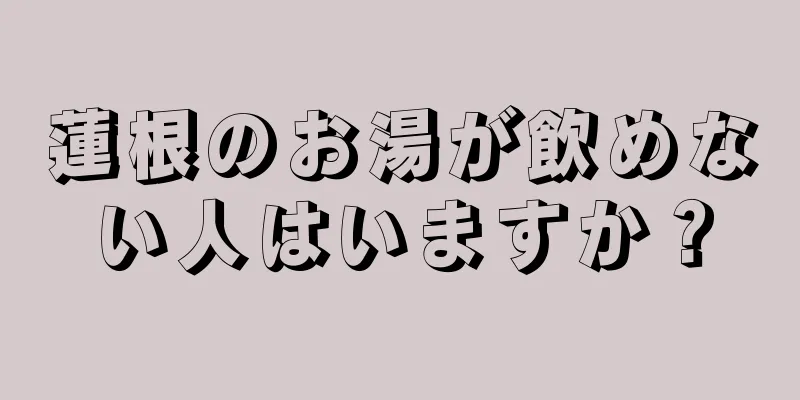妊娠初期にはどのくらいの頻度で検査を受けるべきですか?
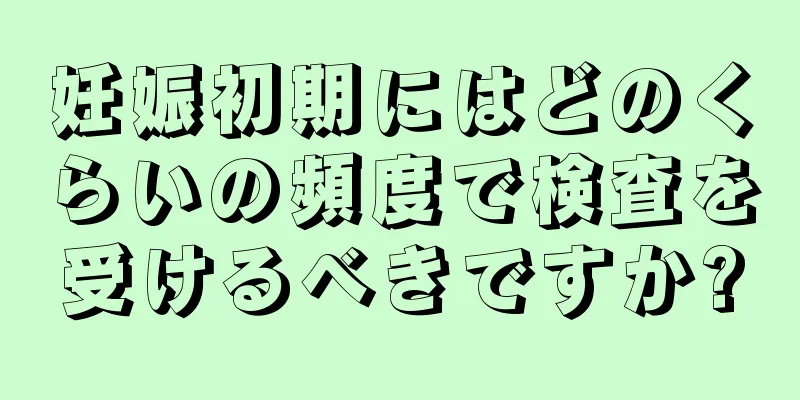
|
妊婦にとって、妊娠初期は体内のホルモンが大きく変動するため、乗り越えるのがより困難な段階です。刺激のある食べ物を食べた時の吐き気や嘔吐など、妊娠初期にはいくつかの妊娠反応が起こりやすくなります。また、身体の疲労や気分のむらなどを感じやすくなります。このとき、心理的な調整を行う必要があり、病院で妊娠検査を行う必要があります。では、妊娠初期にはどのくらいの頻度で検査を受けるべきでしょうか? 妊娠初期にはどのくらいの頻度で検査を受けるべきですか? 妊娠の各段階で、胎児の発育を観察するために、さまざまな項目を検査する必要があります。一般的には、月に 1 回の検査が推奨され、3 か月後に再度検査することが推奨されます。ダウン症候群のスクリーニングは、妊娠 15 週から 20 週に実施する必要があります。切迫流産の場合は、切迫流産の原因に応じて胎児を温存する治療が必要となりますが、絶対安静が必要となります。定期的に出生前検診を受け、体と胎児の発育を注意深く観察し、同時に栄養を強化し、新鮮な野菜や果物を多く食べることをお勧めします。 妊娠初期診断時から、詳細な病歴、総合的な身体検査、産科検査、骨盤計測、B超音波、血液検査、尿検査、心電図、肝機能、腎機能、血液型、B型肝炎・C型肝炎検査、梅毒・HIV検査など必要な補助検査を行い、妊娠20、24、28、32、38、39、40週の計9回の出生前検査を実施します。異常があれば、適宜再検査回数を増やす必要があります。 胎児の発育を観察するためには、さまざまな項目を検査する必要があります。一般的には月に1回検査し、赤ちゃんが3か月になったときに再度検査することをお勧めします。ダウン症候群のスクリーニングは、妊娠15〜20週に行う必要があります。切迫流産の場合は、切迫流産の原因に応じて胎児を温存する治療が必要となりますが、絶対安静が必要となります。定期的に出生前検診を受け、体と胎児の発育を注意深く観察し、同時に栄養を強化し、新鮮な野菜や果物を多く食べることをお勧めします。 検査項目:妊娠12週(3ヶ月)頃に1回目の妊婦健診、13~16週頃に2回目の妊婦健診:ダウン症のスクリーニング。 17〜20週、3回目の妊婦健診。 21〜24週、4回目の出生前検診、妊娠糖尿病スクリーニング。 25〜28週、5回目の妊婦健診。 B型肝炎抗原、梅毒血清検査。 29〜32週、6回目の妊婦健診、下肢浮腫、妊娠中毒症の発生、早産の予防。 33〜35週、7回目の出生前検診、胎児の体重を評価するための超音波(B超音波)検査。 36週目、出産準備のための8回目の妊婦健診。 37週、9回目の妊婦健診、胎動に注意。 38〜42週、10回目の妊婦健診。胎児の位置が固定され、胎児の頭が下がっています。 |
推薦する
帯状疱疹に対する伝統的な漢方薬の処方は何ですか?
帯状疱疹は、男性と女性の両方に発症する可能性のある生殖疾患です。したがって、この疾患に対する科学的理...
足を振ることのデメリット
座っているときに足を揺らすのが好きな人がいます。慣れると無意識かもしれませんが、他の人がそれを見ると...
交感神経を不活性化する方法
交感神経は体の中で非常に重要な神経であり、循環器官、消化器官、呼吸器官において重要な役割を果たしてい...
漢方薬は甲状腺機能低下症に効きますか?
甲状腺機能低下症は甲状腺の病気ですが、この病気が患者に与える影響と害が比較的大きいことは誰もが知って...
消化と吸収の概念
私たちは日々の生活の中で、消化と吸収を絶えず行っています。消化と吸収がなければ、私たちの体は正常に機...
低圧62は正常ですか?
体内には高気圧と低気圧があります。低気圧の正常範囲は一般的に90前後です。低気圧が低すぎると、体に何...
なぜ子供の頃から汗をかくのでしょうか?
子供の頃から汗をかきやすい人がいます。まず考えられるのは、体内に微量元素が不足していることです。子供...
低タンパク質浮腫
検査中に体内のタンパク質が不足していると、浮腫が発生します。重症患者の場合、浮腫がかなり顕著になりま...
姿勢性側弯症には包括的な治療が必要
多くの人は、特に子供は、通常、正しい姿勢に注意を払っていません。親が監督に注意を払わないと、子供は姿...
身長が伸びることに対する反応は何ですか?
人は人生の中でさまざまな段階を経験しますが、ある段階では身体が急速に成熟し、身長が急速に伸びます。こ...
息を吐くと胸が痛くなるのはなぜですか?
息を吐くときに胸が痛む友人は、その胸が痛む原因をぜひ知りたいはずです。では、息を吐くときに胸が痛くな...
舌の下の瘀血はどこにありますか?
舌は人の身体の健康に関係しています。青い静脈は、よく血管と呼ばれます。舌の下の青い静脈と血液の停滞は...
朝、空腹時に牛乳を飲むのは良いことでしょうか?牛乳を飲むのに最適な時間はいつですか?
朝、空腹時に牛乳を飲むのは良いことでしょうか?朝、空腹時に牛乳を飲む習慣がある人がいますが、この方法...
甲状腺刺激ホルモンが低下するとどのような症状が現れますか?
甲状腺刺激ホルモンが低下すると、悪寒、疲労、動作の鈍化、精神的抑うつなどの臨床症状につながる甲状腺機...
これは出産よりも痛いです。
出産が極めて痛みを伴うことは誰もが知っています。女性にとっての出産の痛みは、男性には理解できないもの...