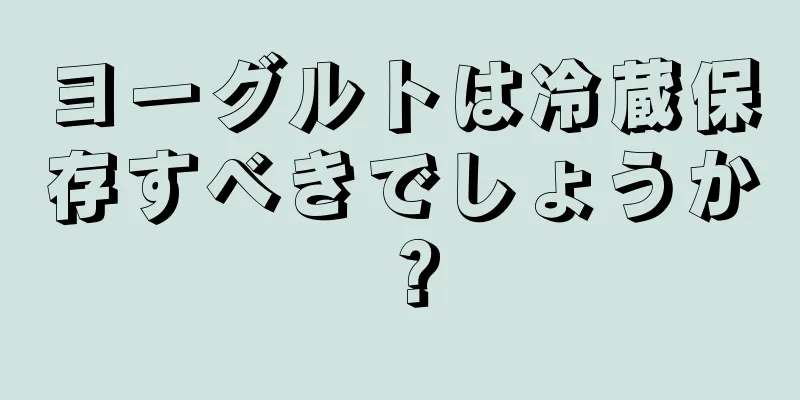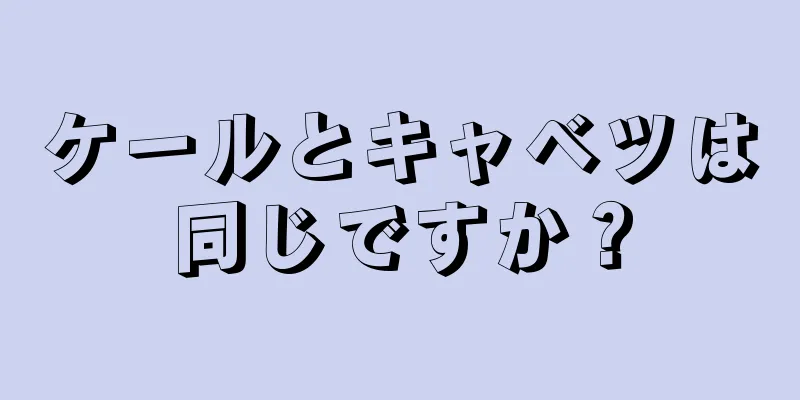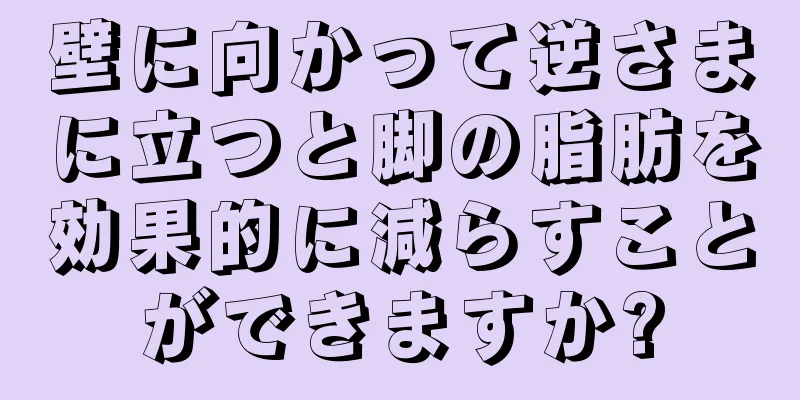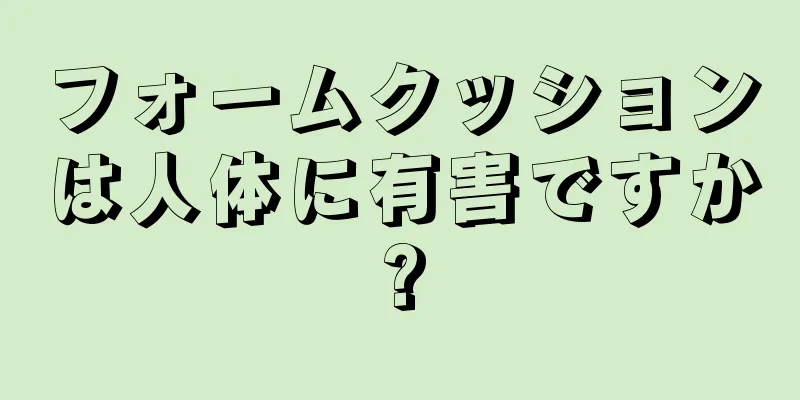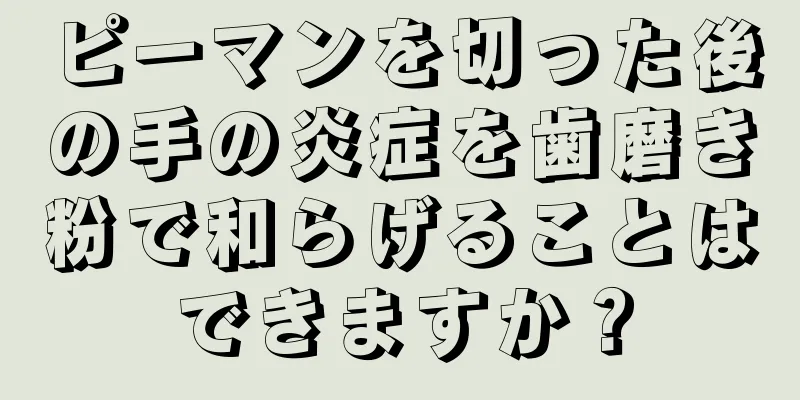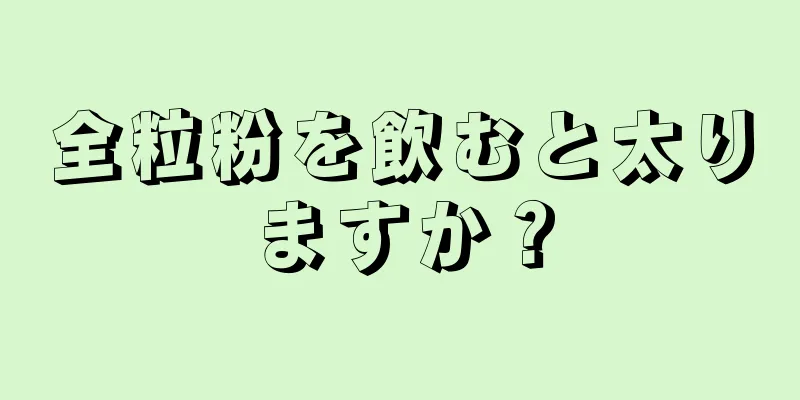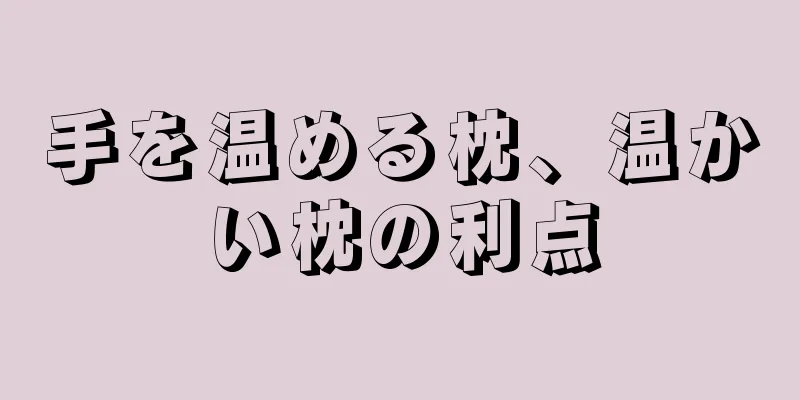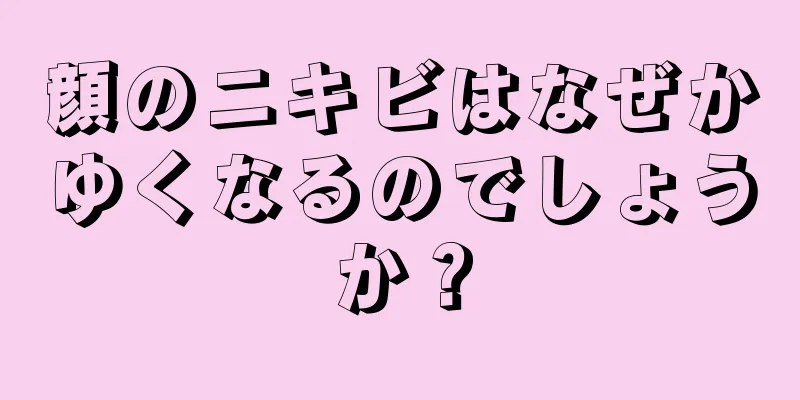排便中におならをする
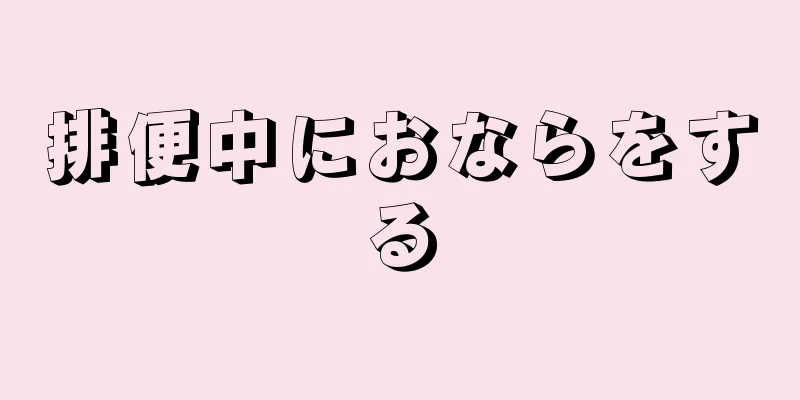
|
多くの人は排便したいときにおならをしますが、これは正常な生理現象です。しかし、排便中にオナラを頻繁にする人、つまりオナラと排便を同時にする人がいます。このような状況が続く場合は、体の腸系に問題がある可能性があるため、注意が必要です。では、排便中にオナラをすると、一体何が起きるのでしょうか? 頻繁に「うんちと一緒におなら」をするのは心配の種である 排便は複数の器官が関与する複雑なプロセスです。頻繁にオナラに便が含まれている場合、ガス、液体、固体の便が制御不能に肛門から排出されていることを意味します。これは「肛門が緩い」ほど単純ではなく、排便システムの他の部分に問題がある可能性があります。一般的に、次の 5 つの部分のうち 1 つ以上の部分に問題がある可能性があります。 1. 緩菊:肛門直腸筋が弛緩し、収縮機能が低下し、筋力が低下します。 2. 排便中枢にバグがある:通常、大便やおならの排泄は脳によって制御されています。エラーがある場合は、排便中枢に問題がある可能性があります。この状況は、アルツハイマー病患者によく見られます。 3. 機械的障害:肛門脱(下降)、内痔核脱(痔核が外に脱出) 4. 手術による括約筋欠損:直腸がん手術や痔核手術による括約筋機能不全など、手術による損傷や出産時の外陰部破裂により生じる局所括約筋欠損。 5. 排便に関連する骨盤底筋の損傷:排便は肛門直腸筋だけでなく骨盤底筋にも関係しています。骨盤底筋組織の損傷によって引き起こされる骨盤底筋機能障害は、放屁や便の排出につながる可能性があります。 オナラに糞が混じる可能性が高いのは誰でしょうか? 医学では、排便器系の障害によりガス、液体、便が制御不能に排出されることを便失禁と呼びます。このような状況に陥りやすいのは誰でしょうか? 出産時に肛門筋が裂傷した女性。 高齢者グループ; 痔の手術など、肛門の手術を受けたことがある人。 特定の薬剤(最も一般的なのは高血圧用のアルファ遮断薬、抗うつ薬、麻酔薬、鎮静剤、睡眠薬)を服用している人。 ひどい便秘に悩まされることが多い人。 炎症性腸疾患(クローン病または潰瘍性大腸炎)の患者。 過敏性腸症候群の人; 神経障害を起こした糖尿病または多発性硬化症の患者。 脳卒中およびアルツハイマー病患者。 |
推薦する
5つの舌の表現はあなたが怒っている場所を示します
伝統的な中国医学では「観察、聴診、問診、触診」を重視しており、その中でも「観察」による診断は最も学び...
女性の卵子は食べられるのでしょうか?
社会の発展と進歩に伴い、人々の生活環境はますます良くなってきており、それは喜ばしいことです。しかし同...
塩水を多く飲むとどんなメリットがありますか?
塩水を毎日適度に飲むと一定の効果がありますが、飲むタイミングをきちんと選ばなければなりません。朝早く...
彼の財産の半分以上が消えた!ザッカーバーグ氏は7年ぶりに世界長者番付のトップ10から脱落した。
<span data-docs-delta="[[20,"获悉,福布斯杂志在其最新一...
家具にホルムアルデヒドが含まれているかどうかを判断する方法
周知のように、ホルムアルデヒドは人体にとって極めて有害です。この有害物質は白血病やガンの原因にもなり...
皮膚テストアレルギーの症状は何ですか?
人によって体質が異なるため、使用する薬も異なります。薬によってはアレルギー反応を起こす人もいるため、...
バドミントンを学ぶのに最適な年齢
バドミントンは全国で人々がプレーするスポーツです。バドミントンは人間の協調性と柔軟性を向上させるのに...
肺がん治療薬
肺は人体にとって重要な臓器であり、人間の呼吸に直接影響を与える臓器です。肺がんも非常によくある病気で...
皮膚がんをよりよく予防する方法
皮膚がんの脅威は比較的大きいため、日常生活において、誰であっても、皮膚がんを予防するためのいくつかの...
血小板はわずか17
血小板数はわずか17で、血小板数が少ないことを示しています。もちろん、血小板数の低下は患者に大きな影...
木材防腐処理の方法は何ですか?
日常生活では、木材は摩擦により腐りやすく、内部に虫が繁殖する傾向があります。そうなると、木材の品質は...
耳から流れる清らかな水
耳は人体で最も重要な部位の一つです。最も一般的な中耳炎や、耳鳴りなどの他の病気など、耳に発生する可能...
腰靭帯が損傷したらどうすればいい?ケア方法はこの4つ
腰靭帯の捻挫は、主に日常の運動、特にしゃがんだり物を持ち上げたりするときの不注意が原因で起こり、腰靭...
リブをこのように炒めると、シンプルで美味しいです
スペアリブは、とても一般的な料理です。煮込み、蒸し煮、鍋料理のほか、スペアリブも作ることができます。...
傷跡が自然に消えるまでには1年かかりますか?
傷跡は簡単に形成され、一瞬で大きくなることもありますが、傷跡の回復を促進する効果を得るには、回復期間...