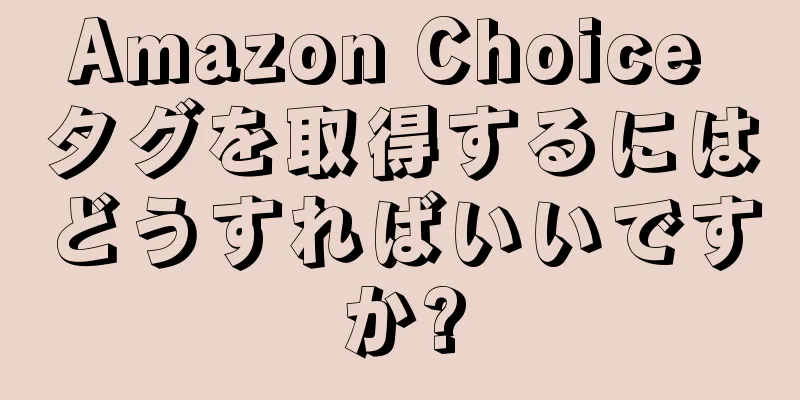北向きと南向きのどちらで寝るのが良いでしょうか?ベッドを置くときに注意すべきことは何ですか?

|
科学的観点から見ると、南北方向に寝るのが良いですし、体内の血液循環を促進することもできます。地球の磁場は南北方向にあるため、寝る方向を決めるには地球の磁場に従わなければなりません。人の睡眠状態はベッドの配置とも深く関係しているため、ベッドの配置も無視できない問題です。 まず、ベッドの頭側を窓の下に置かないでください。そうしないと、寝ているときに不安を感じてしまいます。強風や雷雨があれば、この感覚はさらに強くなります。また、窓際は空気の対流が強く、窓の下で寝る人は注意しないと風邪をひいてしまうこともあります。 ベッドの頭側は寝室のドアに面してはいけません。そうしないと、リビングルームの人が寝室のベッドを一目で見ることができ、寝室に静けさがなくなり、休息に影響します。さらに、ベッドに横たわっているときに頭を上げるとすぐにリビングルームの動きが見えてしまい、落ち着いて眠りにつくのが難しくなります。 最後に、ベッドの頭側は東または西を向いてはいけません。これは、地球の地磁気の方向が南北であり、磁場が鉄、コバルト、ニッケルなどの金属を引き付ける性質があるためです。人体にはこれら3つの元素が含まれており、特に血液には大量の鉄が含まれています。そのため、東西向きで寝ると、体内の血液の分布、特に脳内の血液の分布が変わり、不眠症や夢見を引き起こし、睡眠の質に影響を与えます。 部屋のレイアウトを変えることはできませんが、寝室を合理的にレイアウトし、ベッドを科学的に配置することで、静かで快適な睡眠環境を作り出すことができます。ベッドを配置する科学的な方法は、ベッドを南北方向に置き、ベッドの片側または両側を壁につけることです。ダブルベッドの両側に歩行スペースを残しておくと、ベッドの出入りがしやすくなり、ベッドメイキングもより便利になります。 |
>>: なぜ睡眠が必要なのでしょうか? 睡眠の利点は何でしょうか?
推薦する
顔が乾燥しているときに素早く水分補給する方法
顔が乾燥している場合は、適時に水分を補給する必要があります。良好な水分補給効果を得るために、採用でき...
生理中の不機嫌を和らげる方法
女友達は月経期間中、月経困難症、不機嫌、食欲不振など多くの合併症に悩まされます。これらの月経合併症、...
ランニング中にふくらはぎの前側の筋肉に痛みを感じる
筋肉痛は、間違った走り方や間違った力のかけ方によって引き起こされることがあります。ランニングをすると...
アマゾンの偽注文騒動をメディアが暴露!当局は厳しい取り締まりを開始する予定だ
Amazon が偽造注文をどれほど厳しく取り締まっているかを知るには、米国サイトの販売者に聞いてみ...
肝臓障害の4大原因にご注意!
正常な肝機能は人間の健康を維持します。肝機能が損傷すると、人間の健康に大きな影響を与えます。肝臓障害...
人間の赤い炎症
人中は、人々が非常に重視する部分です。主に唇の上と鼻の下の皮膚組織の垂直列にあります。人中の内部の神...
キャベツとキャベツの違い
牛心キャベツとキャベツは同じ料理ではありません。牛心キャベツはキャベツとも呼ばれ、比較的一般的な野菜...
額に斑点ができる原因は何ですか?
多くの人は額にシミがありますが、この場所のシミは非常に目立ち、髪で隠すことができないため、彼らにとっ...
健康診断のためには早く寝る必要がありますか?
健康診断のためには早めに寝る必要がありますが、その際には検査結果の精度を高めるためにクラス3Aの病院...
胸の谷間の真ん中に硬いしこりがあり、押すと痛い
胸の谷間の真ん中に硬いしこりができ、押すと痛いことがあります。何が起こっているのか分からない人が多い...
売り手は注意してください!アマゾンが2つのFBA倉庫を閉鎖、販売者は近い将来出荷できなくなる可能性
最近、北米Amazonの販売業者は非常に落ち込んでいます。アカウント補充制限に続いて、米国サイトでは...
かかとに水ぶくれができたらどうするか
人生の中で、多くの人が新しく買った靴を履いた後にかかとに水ぶくれができた経験があります。この現象には...
セフトリアキソンは腸炎を治療しますか?
セファロスポリンは、どの家庭の救急箱にも必ず入っている抗生物質です。セファロスポリンは主に抗炎症作用...
顔に汗をかくことは肌に良いのでしょうか?
夏は汗をかく季節です。汗をかくことでダイエット効果が得られるほか、デトックス効果や美容効果も得られま...
歯茎が腫れて膿が出たらどうすればいい?
ひどい歯茎の腫れや痛みは、歯茎に膿がたまる原因となることがあります。これは歯茎に瘀血が溜まるためです...